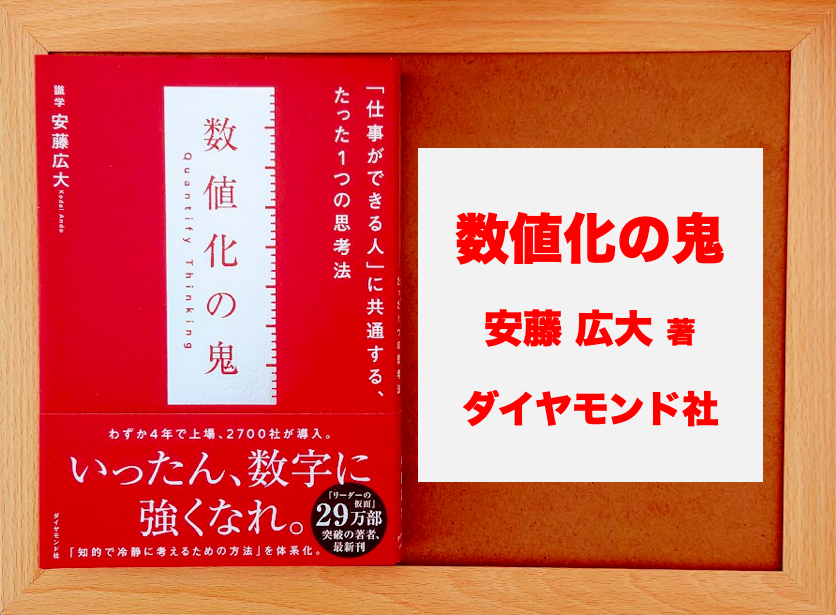
【数字と向き合うほど、成長は加速する!】
識学・安藤広大氏が、『数値化の鬼』と題して、「仕事ができる人」ほど「数字に強い」と提起し、自分の成長のために、数字で考えられるようになる思考法を指南する一冊。
■書籍の紹介文
「今日、何回スマホを触りましたか?」
急に問われて、パッと答えられるでしょうか。
本書は、数字と向き合う回数が増えるほど人も組織も成長すると提起し、「識学」という意識構造学を通じて「数字で考える思考法」を徹底指南する一冊。
冒頭の問いに、「いつもより多めかな」「別に何回でもいいじゃん」と”感情”で答えるか。
「寝起き、通勤時、仕事前、・・・の約10回ですね」と”数字”で答えるか。
どちらで答えられるかによって、人の成長スピードに圧倒的な差が生まれる。
そういう話をテーマにした書籍です。
読んでいて、「読書時間をどう捻出するか問題」にそのまま当てはまるなと感じました。
感情型の人は「なかなか忙しくって難しい」、数字型の人は「30分はスキマ時間確保できそうなので読書に充てます」と、お答えになる傾向が強いように感じます。
「忙しい」「難しい」などと”抽象的”に考えていても行動できません。
一方で、日々の行動を数値化できていれば、”具体的”に考えられて行動をあてはめられます。
読書が成長に有益なことに異論はないとおもいます。
つまり、読書時間の捻出ひとつとっても、数字型の人のほうが成長スピードが早いといえるのです。
両者の差は、数字で考えられているかどうかだけです。
いうまでもなく、数字はだれが見てもあきらかな「”客観的”事実」です。
「読書に充てたい時間」と「現状の1日の時間の過ごし方」。
「数字」を持っているからこそ、”客観的”に調整できるのです。
現状の1日の使い方を見直したけど、どう見直しても満杯である。
こう客観的に理解できれば、既存の行動を削るか、読書を保留するか、といった”具体的”な検討ができるわけです。
要するに、「数字」を持つことで、感情に左右されず、客観的に考えられるのです。
数値化するクセをつけることで、自分の今の状況をありのままに受け入れる”覚悟”がつくのです。
「数字」という事実があれば、「自分の足りないところ」が見えてきます。
受け入れたくない姿も浮かびあがるでしょうが、心を”鬼”にして、受け入れることで成長ははじまるのです。
このように、どんなことでも『いったん数字で考える』ことをクセづけておく。
どんな状況でも「いったん数字で考える」「正しく数える」「数値化した評価をする」「時間やコストの感覚を持つ」など、数字で考えることを意識する。
これがあたりまえの状態になれば、成長スピードは加速度的に増していきます。
本書では、数字で考えられるようになるポイント(数値化の方法)を徹底解説しています。
◎行動量
◎確率
◎変数
◎真の変数
◎長い期間
この5つが学習の肝になります。
難解な数式や専門的な知識は必要なく、純粋な読み物として読めますので苦手意識のある方も安心してください。
『順番を間違えるな』
何度となく出てくるこのフレーズが、とくに印象に残ります。
数字で考えることの本質も理解せずに疎かにすると痛い目に合うぞ。
そう、現代社会に警鐘を鳴らす一冊です。
◆数字に強くなれ。
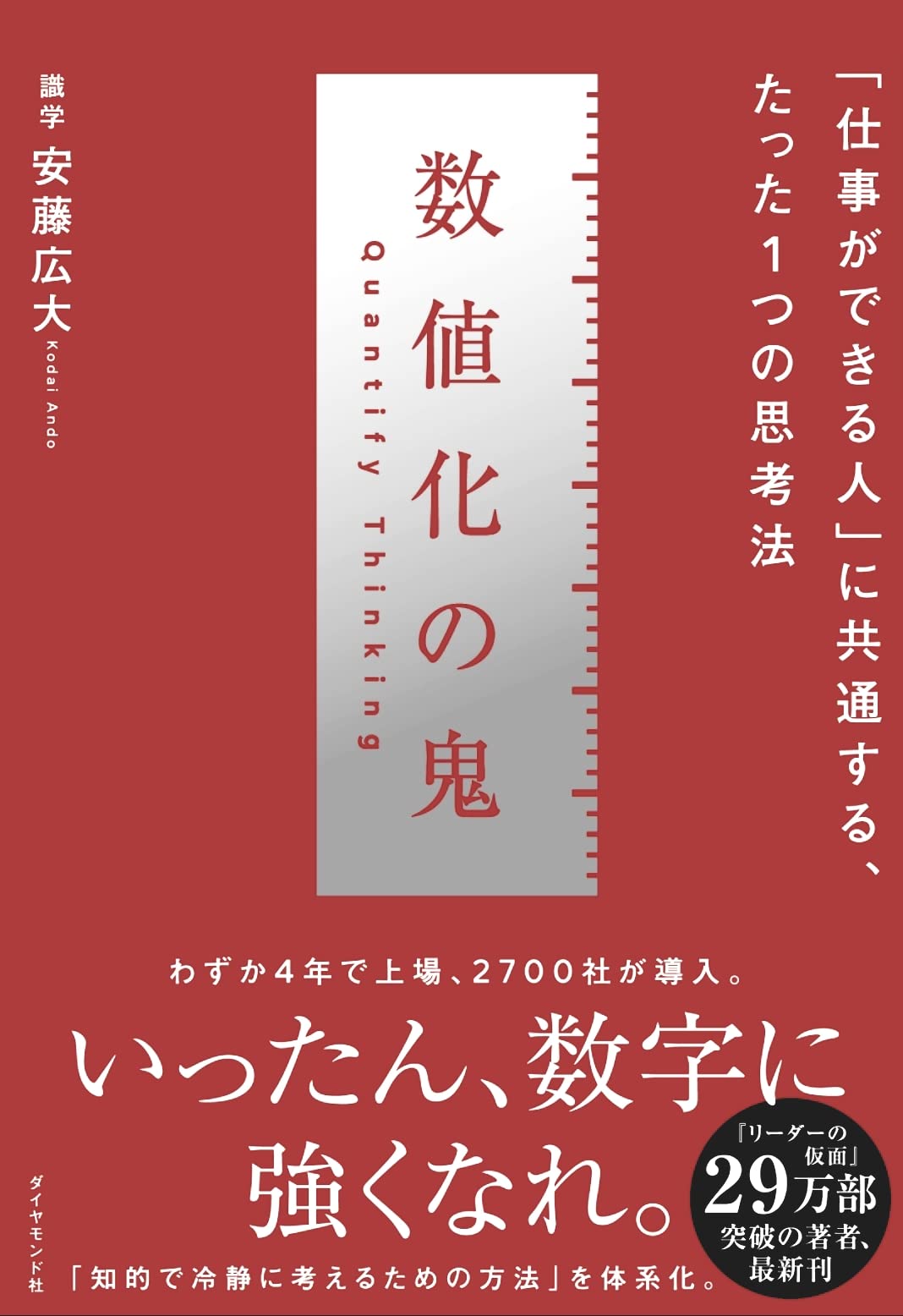
数値化の鬼
安藤広大 ダイヤモンド社 2022-3-2
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
なぜ、数値化をするのか、それを考えてみましょう。
それは、「未来」に目を向けるためです。
「数値化された評価を受け入れる」
「自分の不足を数字として受け入れる」
この2つさえ理解できれば、「主体的」な数値化のノウハウで自分の仕事に取り組むことができます。
ホームランを打てば、その日の三振のことは観客の誰もが忘れてしまうように、大きな成功を生み出すと、それまでの失敗は誰も覚えていないものです。
だから、まずは誰よりも数をこなす。
「行動量」を増やす。
PDCAの「D」を増やす。
日々の行動に迷いがないレベルにまで「KPIに分解できていること」が重要です。
量をこなすと、次は、質にこだわるのは当然でしょう。
そのこと自体は問題ではありません。
しかし、「量」よりも「質」が上回り、「質を上げること」が目的になってしまうことは大問題です。
あくまで「行動量ファースト」であり、それをキープしたまま「確率も上げていく」というのが正しい順番です。
この順番を間違えてしまうのが、「働かないおじさん」への第一歩なのです。
計算の仕方によって印象を操作したいときに、「%」は便利です。
それを理解した上で、ダマされないようにすべきです。
そのための口グセとして、
「この%は、何分の何ですか?」
という確認が便利です。
相手から説明されないときは、何かしら隠しておきたい「意図」があると思って間違いないでしょう。
工程を分けて、数字をかぞえて、「なぜ?」を繰り返す。
頭の中で妄想するのではなく、実際に行動した数字から考えていくのがポイントです。
いかなるときも、「P(目標)」が何かを忘れないことです。
そして、それに対して行なった「D」に対して数字としての成果があったかどうかが大事です。
変数を見つけ出す過程で、最終的には「1つに絞ること」を忘れないことが大事です。
とにかく迷ったら「変数」で考える
「5年後の姿」と「今日のKPI」はつながっています。
行動量さえ落ちていなければ、数字の結果はちゃんとついてきます。
・目標は達成しているけれど、行動量が落ちているプレーヤー
・目標は達成していないけれど、行動量が増えているプレーヤー
これを長期的な目線で評価すると、後者のほうが確実に成長します。
・「数字の成果」→「自分らしさ」
・「数字の根拠」→「言葉の熱量」
・「まずやってみる」→「理由に納得する」
・「チームの利益」→「個人の利益」
・「行動量を増やす」→「確率を上げる」
・「長期的に考える」→「逆算して短期的に考える」
数字に表れない「やりがい」や「達成感」は、数字を追いかけた先で、ふと振り返るとついてきているものです。
そして、その逆はありえません。
■【実践】3個の行動ポイント
【1836-1】行動や目標は、必ず数字を入れて設定する
【1836-2】目標につながる変数は、1つに絞って設定する
【1836-3】数字の分析は、変数を使って行う
■ひと言まとめ
※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】数値化の鬼
【著者名】安藤広大 ・ 著者情報
【出版社】ダイヤモンド社
【出版日】2022/3/2
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】明日の仕事力を磨きたいときに
【キーワード】思考、数学的思考、働き方
【頁 数】288ページ
【目 次】
序章 「数値化の鬼」とは何か
第1章 数を打つところから始まる
第2章 あなたの動きを止めるもの
第3章 やるべきこと、やらなくてもいいこと
第4章 過去の成功を捨て続ける
第5章 遠くの自分から逆算する
終章 数値化の限界
この本が、あなたを変える!
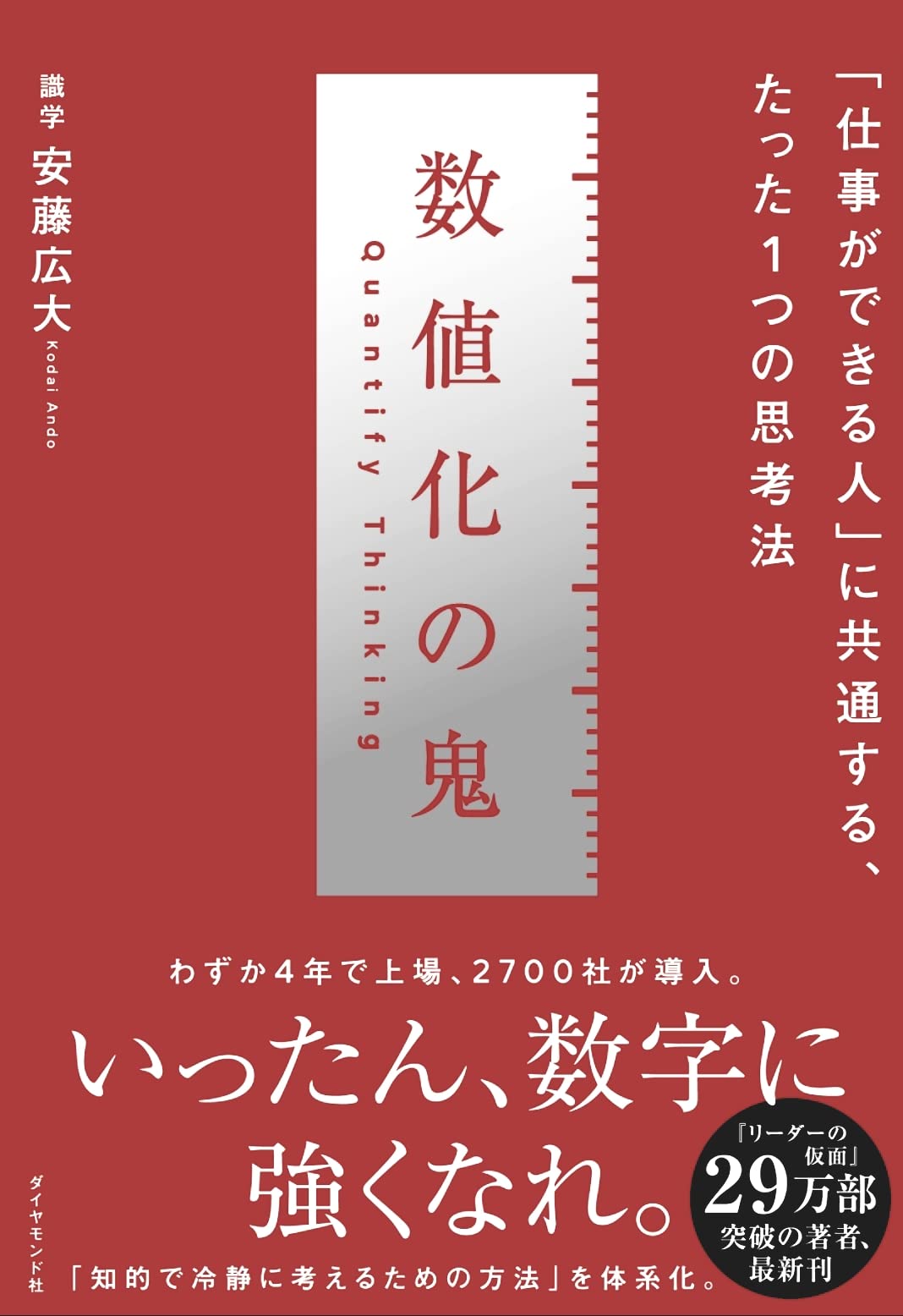
数値化の鬼
安藤広大 ダイヤモンド社 2022-3-2
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
安藤広大さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2022年 4月 19日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(4/11〜4/17)
-
2022年 4月 25日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(4/18〜4/24)
-
2022年 5月 01日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキング(2022年4月版)
-
2022年 5月 17日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(5/9〜5/15)
-
2022年 5月 24日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(5/16〜5/22)
-
2022年 5月 30日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(5/23〜5/29)
-
2022年 6月 07日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(5/30〜6/5)
-
2022年 6月 16日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(6/6〜6/12)
-
2022年 6月 21日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(6/13〜6/19)
-
2022年 6月 28日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(6/20〜6/26)
-
2022年 7月 07日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(6/27〜7/3)
-
2022年 7月 12日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(7/4〜7/10)
-
2022年 7月 18日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(7/11〜7/17)
-
2022年 8月 01日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキング(2022年7月版)

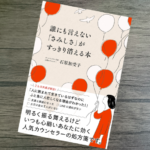
この記事へのコメントはありません。