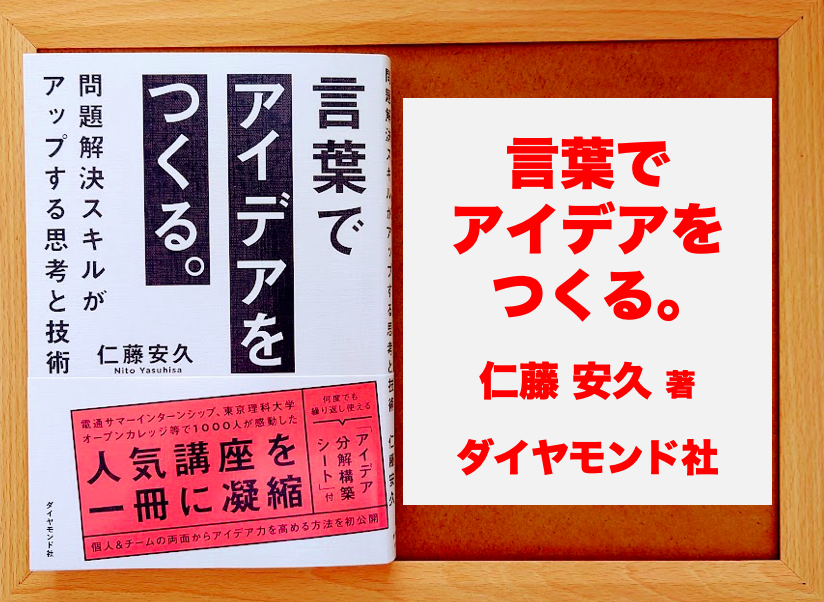
【探すのは「正しい答え」ではなく「正しい問い」】
コピーライター・仁藤安久氏が、『言葉でアイデアをつくる。』と題して、アイデア出しで大切なのは”問い”であると提起し、アイデアを出す力を高める方法を解説する一冊。
もくじ
■書籍の紹介文
アイデアを出す。
どんなときにこの行為は発生しますか?
本書は、アイデア出しで大切なことは「正しい答え」を探すことではなく「正しい問い」を探すことだと提起し、誰でも実践できる、アイデアを出す力を高める方法を解説する一冊。
アイデアを出そうとおもうとき。
そこには必ず、解決しなければならない”何かしらの問題”が横たわっているはずです。
つまり、『○○という問題を解決するには、■■が必要である』。
この■■に当てはまるモノを考える行為こそが、「アイデアを出す」ことだとおもいます。
ただ、このとき注意すべきことがあり、それは本書の教えの要ともいうべきものです。
なにかと言うと、”当てはまる”に囚われて「ピタリとハマる”正解”を探すマインド」に陥らないことです。
「正しい答え」を探そうとするほど、アイデア出しは苦しくなる。
著者は、そう力説しています。
では、アイデア出しのためにはなにが必要なのか。
もう一度、『○○という問題を解決するには、■■が必要である』を確認してみてください。
お気づきになりますか。
そう、アイデア出しで大事にすべきは、■■の部分ではなく○○の部分なのです。
えっ?○○の部分って、解決したい問題(問題だと認識していること)が入るだけでしょ?
あなたは、そう思ったかもしれません。
そこで著者は問います。
「あなたが認識しているその問題、本当に真の問題なのですか?」と。
問題(だと思っていること)の裏側に、もっと本質的な解決すべき問題が隠れているのではないか。
アイデア出しをする際、この視点は絶対に持っておくべきだということです。
要するに、はじめの問題設定=「正しい問い」を立てることが何より重要なのです。
本書では、そのために必要な技術を解説しながら、技術を身につけ磨くのに役立つ方法を指南していきます。
チャートやコピーしてすぐに使えるシートなど、実用性も高いつくりになっています。
本来、アイデアとは専門家の特権ではなく、だれもが出せて生かせるものであるはずです。
苦手だと逃げずに、ぜひ自分のアイデアを出す力を高めましょう。
374ページと分厚いですが、とても読みやすく没頭できる一冊です。
◆無駄のない凝縮された良書。
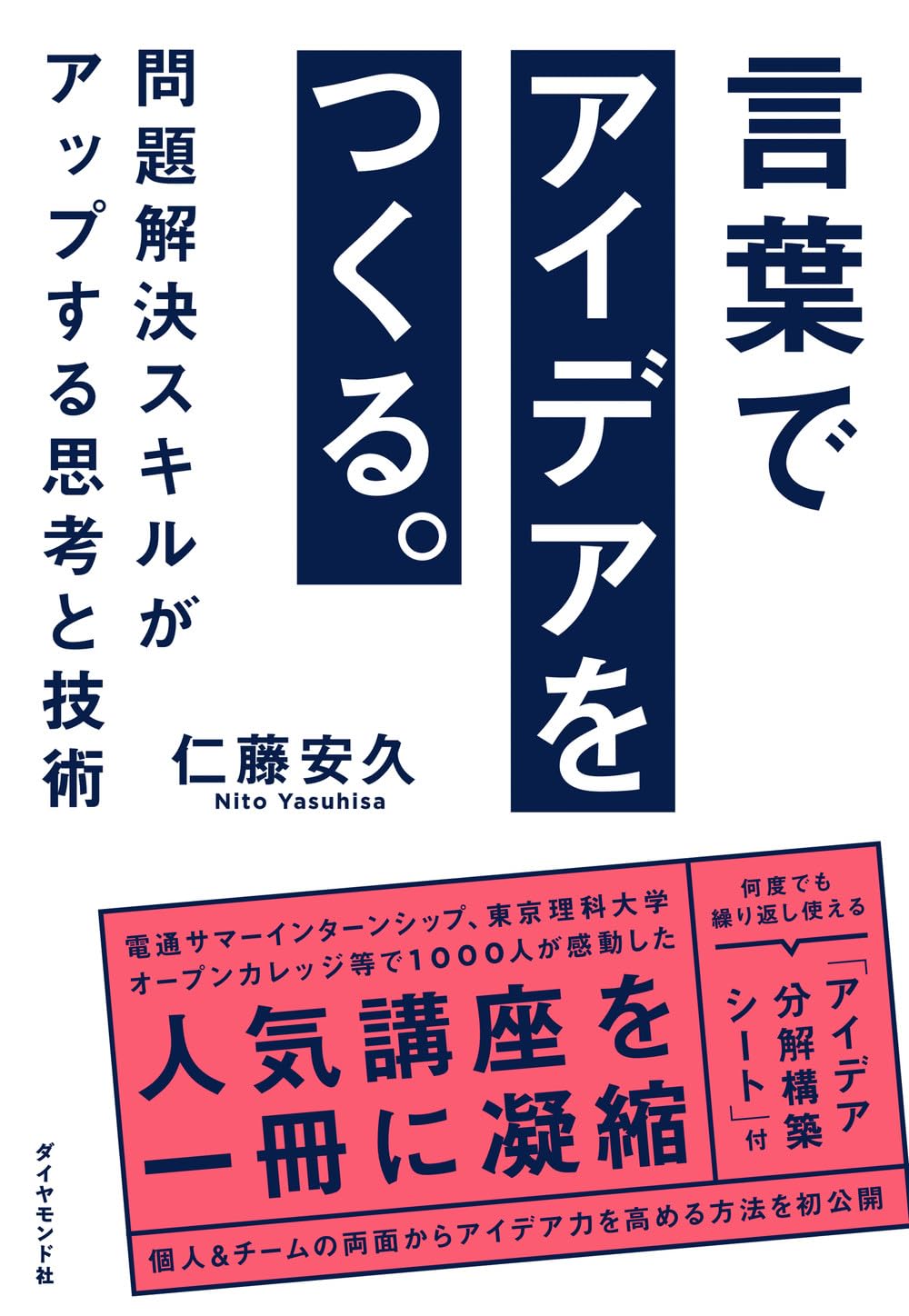
言葉でアイデアをつくる。
仁藤安久 ダイヤモンド社 2024-3-12
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
ブレーキは、あなたのココロに存在します。
そして、そのブレーキを外すための方法はひとつです。
それは、「私にもアイデアは出せる」と自分を信じることです。
課題を出されたときに、いきなり答えを考えはじめるのではなく、本当の課題は何かと疑い、質問を投げかけていくことこそが、いいアイデアを生みだすための近道でもあるのです。
●アイデアが生まれる原理
1.アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ(コンビネーション)であること
2.既存の要素を新しい1つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性を見つけ出す才能に依存するところが大きい
言葉をどう使うかによって、アイデアの発想力も精度も変わってきます。
私が「言葉でアイデアをつくる」ことを大切にしている理由があります。
それが、
「言葉にすることで、アイデアの不完全さに気づく」
ということです。
私がよく行うのは、ワークシートをつくり「これを埋めれば企画ができる」という穴埋め文章をつくる方法です。
<ワークシートの基本形>
【 課題 】という課題に対して、
【 手段 】をして、
【 目的 】というアイデア。
その結果、【 1次的成果 】という成果を生み、
それは、【 2次的成果 】に結びつく。
ヒットする条件をあえてひっくり返して、制約をつくることで、そこから新しいアイデアやコンセプトをつくる
アイデアを生みだそうと思ったときには、「正解はひとつではない」ことがほとんどだという前提に立つことが大切です。
●停滞したアイデア出しの現場を変える方法
①チームをさらに小分けにする
②議論の過程を可視化する
③アナロジーの問いかけを行う
④最低のアイデアを出して結論づけようとする
いいアイデアを選ぶときに、ただ構造的に正しそうなものを選びがちですが、これは違います。
徹底的に、消費者やユーザー側の視点に立って、アイデアを選ぶべきなのです。
●インサイト(※)の発見力を鍛えるための3つのアプローチ
(1)自分のココロに耳を傾けること
(2)他者を観察すること
(3)調査や分析レポート、論文や書籍から、普遍的な心理、世代における価値観の違いなどを把握していくこと
(※)人間の行動や態度の根底にあるホンネや核心などの”気づき”
アイデアを共有する際に大切になってくるのは、抽象的な概念だけではなく、そこに具体性が含まれていることです。
わかりやすく言うと、「抽象→具体」の順番で話をしていくことが大切です。
言葉は、「正しく言い表して伝える」ことよりも「どう伝わるか」を意識することが大切になってきます。
言葉を受け取った側の想像力が掻き立てられて、その未来にワクワクできるかは「具体の言葉」のところにコツがあります。
情報の消費のスピードが速くなっている中で、私は「消費されない消費はつくれるのか」ということを問いとして持っています。
チームにおいては、その「なんとなく好き」「なんとなくいい」という発言を許容することが大切です。
そのひとりの直感に向き合い、なぜ、そう思ったのか、チームみんなで探求していくことが、そのアイデアの根底にあるインサイトなどを発見していくことにつながっていくからです。
■【実践】3個の行動ポイント
【2102-1】アイデアを考えたら、最終的にそのアイデアに1行で名前をつける
【2102-2】アイデアを伝える際、汎用的な言葉は避けて具体的な言葉を使う
【2102-3】「なんとなく」という感覚を大切にする
■ひと言まとめ
※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】言葉でアイデアをつくる。
【著者名】仁藤安久 ・ 著者情報
【出版社】ダイヤモンド社
【出版日】2024/3/12
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】考える力を身につけたいときに
【キーワード】アイデア、発想力、問題解決
【頁 数】374ページ
【目 次】
第1章 「アイデア発想法」の前に必要なこと
第2章 「アイデア発想」の基礎技術
第3章 「アイデア発想」の応用技術
第4章 チームでアイデアを生みだす技術
第5章 「いいアイデア」を見極める技術
第6章 アイデアの実現を加速させるための仲間を増やす技術
第7章 成長しつづけるためのアイデア
▼さっそくこの本を読む
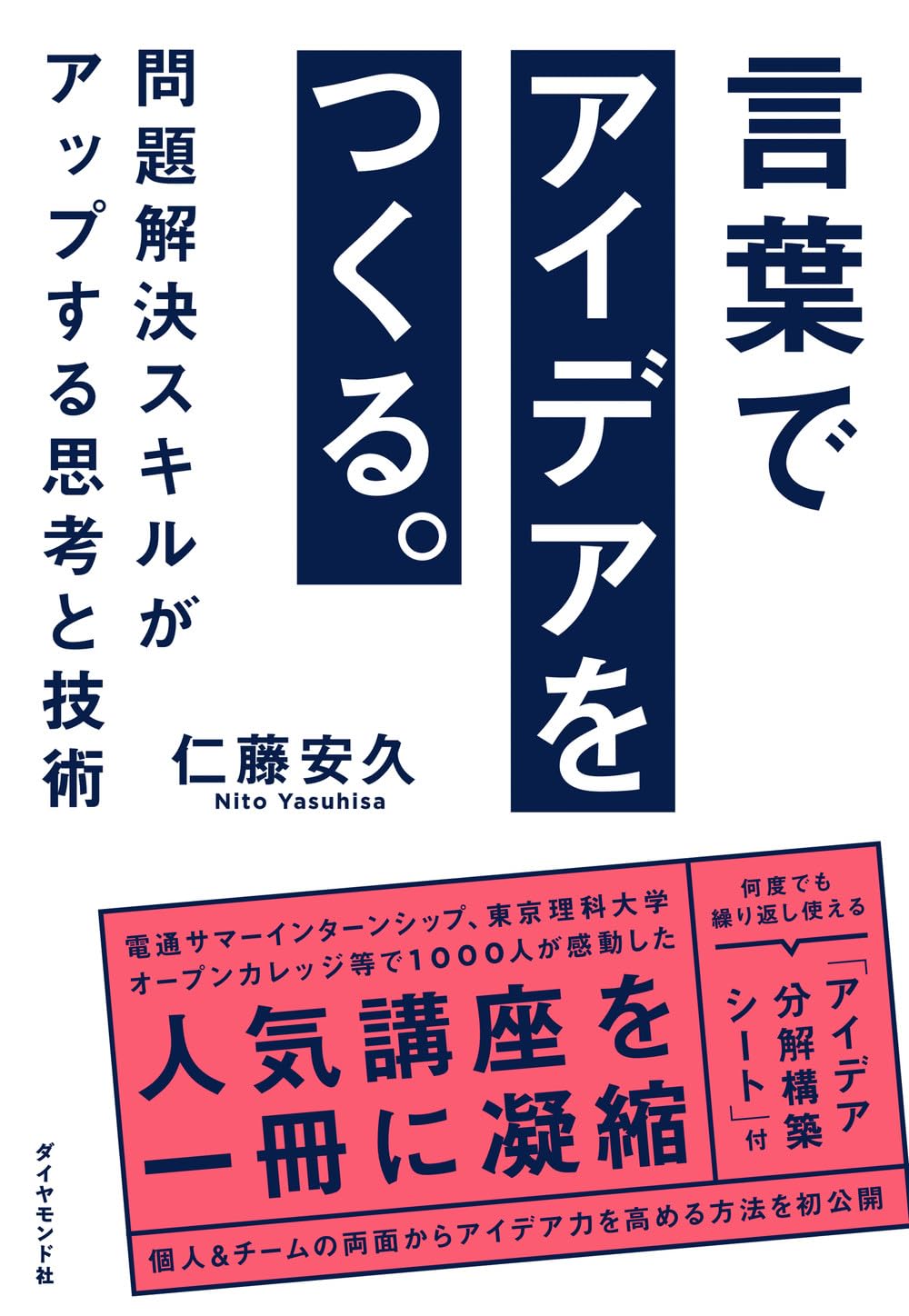
言葉でアイデアをつくる。
仁藤安久 ダイヤモンド社 2024-3-12
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
仁藤安久さん、素敵な一冊をありがとうございました!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2024年 6月 25日


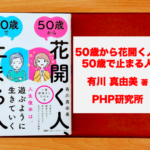
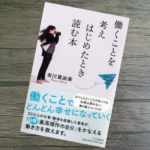

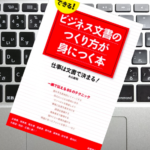
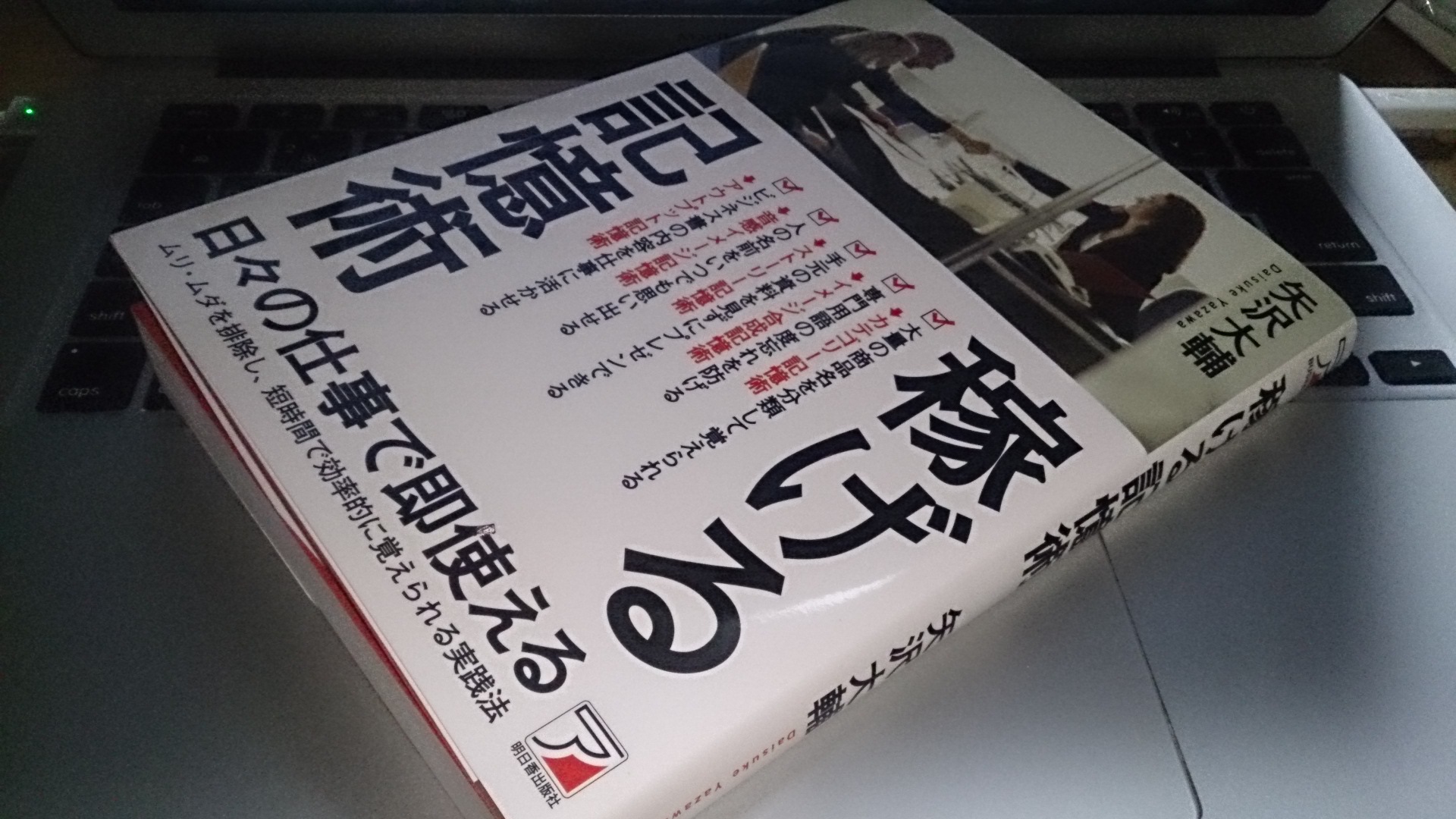
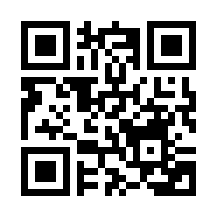
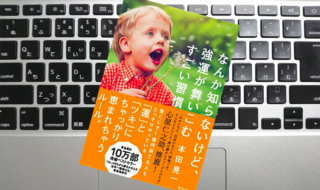
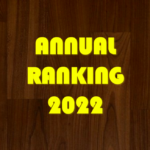

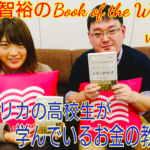
この記事へのコメントはありません。