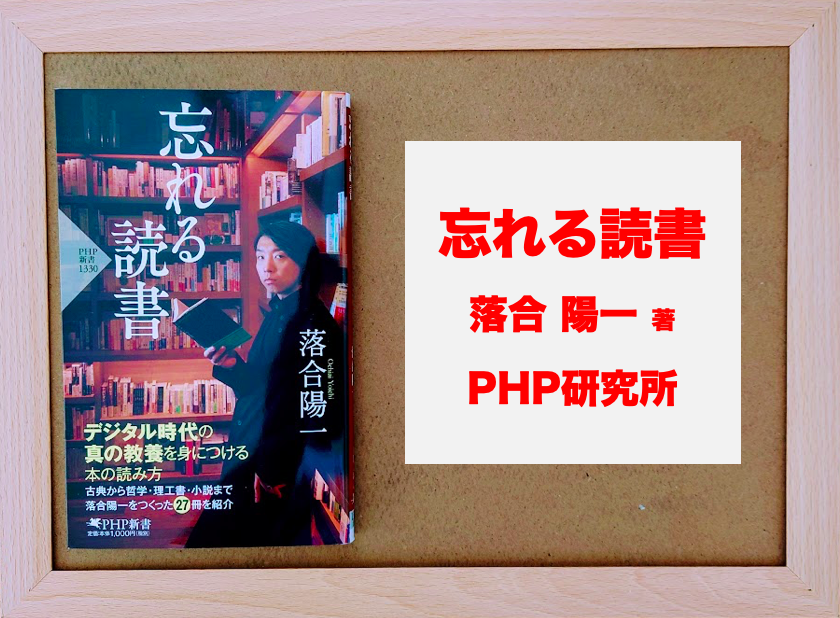
【持続可能な教養を養えるのは”読書”だけ!】
メディアアーティスト・落合陽一氏が、『忘れる読書』と題して、著者独自の読書法や推薦図書を明かしながら、本の読み解きで磨く”時代を生き抜く思考法”を解説する一冊。
■書籍の紹介文
本を読むべき理由。
あなたはなんだと考えますか?
本書は、著者独自の読書法や推薦図書を明かしながら、本の読み解きを通して、どんな時代も生き抜いていく思考を養う方法を解説する一冊。
先行きのわからない時代には、新しい教養が必要だと著者は主張します。
この新しい教養を「持続可能な教養」と定義します。
「持続可能な教養」とは、つぎの2つのことを鍛えることだといいます。
まずは「物事を抽象化する思考」、つぎに「気づく能力」の2つです。
では、これらをどうやって鍛えればいいのか。
ここで推奨されるのが『読書』です。
なぜ『読書』が有効なのかを、知的好奇心を刺激する文章を通して説いていきます。
さらに、各章ごとに推奨図書をリストアップしているのでブックガイド本としても楽しめます。
重要なのは、ウェブの細切れの情報に触れるだけでは教養は身につかないということ。
このことを決して忘れてはいけないのだ、ということを改めて実感しました。
著者の読書遍歴に触れることで、「だから本を読むのか」という答えが見えてきます。
また、本との向き合い方がイマイチ定まらない・・・、そうした方にヒントの多い内容に感じます。
深いけれど、読みやすい。
『読書』へと誘う本を、ぜひ『読書』してみてください。
◆脳が喜ぶ良書。
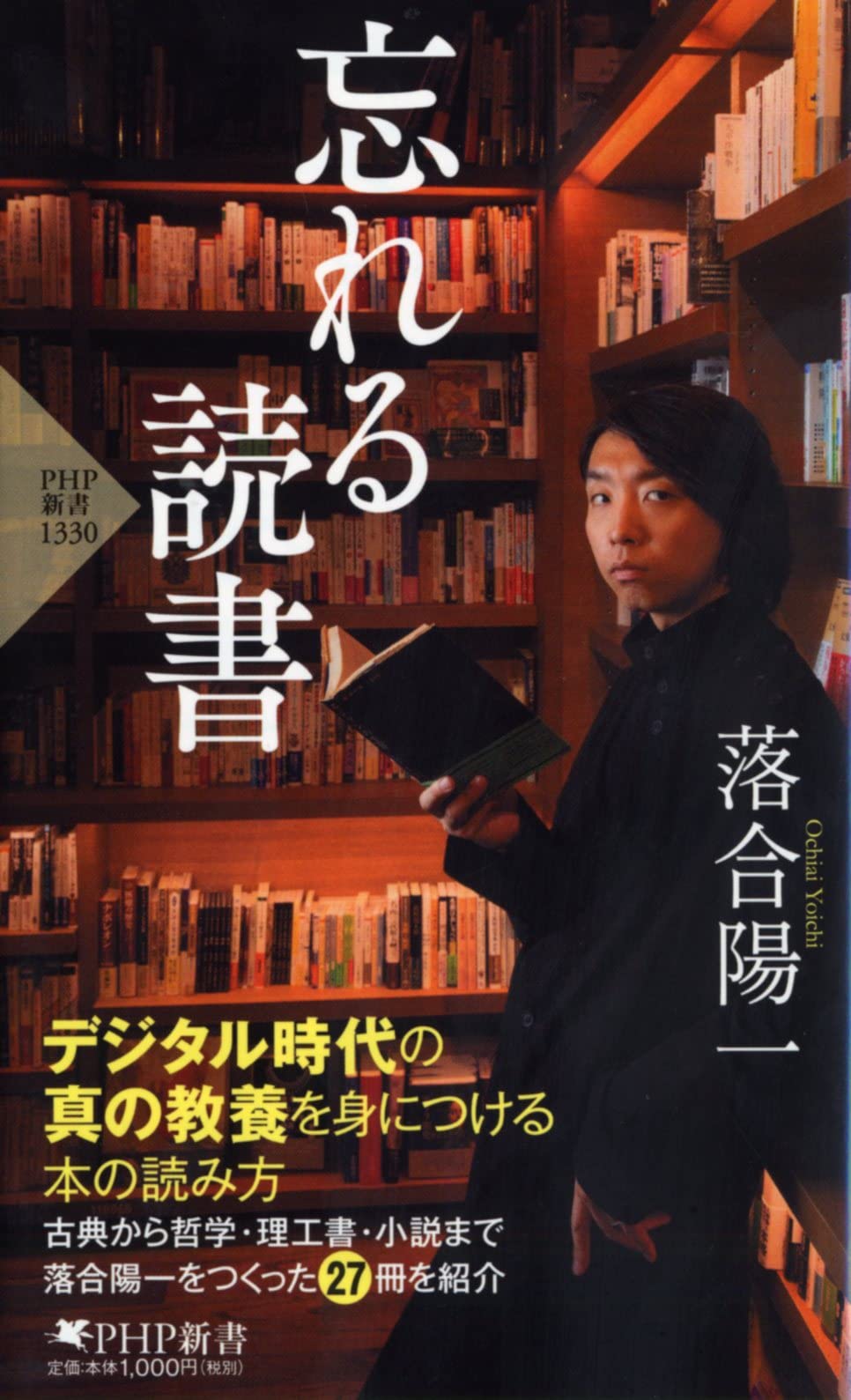
忘れる読書
落合陽一 PHP研究所 2022-10-27
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
教養とは「抽象度の高いことを考える力」と「知識と知識をつなぎ合わせる力」であり、それらを磨くには読書が最適だと書きました。
これはアーティストが日々使っている「自分でストーリーを練り上げる力」とほぼ同義だと私は考えています。
自分のストーリーを練り上げるとは、つまり抽象化しながら思考し、点在する知を自分の文脈でつないで物語化するということです。
何から読んでいいのかわからない・・・という悩みは、よく耳にします。
そういう場合は岩波文庫で「見聞きしたことのあるタイトルだけれど中身は読んだことがない」といった本に挑戦してみるのがいいでしょう。
おそらく何かしら、自分の文脈が見出せるはずです。
●物事の読み解きに必要な「3ステップ」
(1)圧縮された一次情報に一度触れてみる
(2)しばらくしてから、雰囲気を掴むために、もう一度必要なところを見返す
(3)情報と情報とを並べて俯瞰してみる
これからの時代、クリエイティブであるための知的技術は、読後に自分の中に残った知識や考えをざっくりと頭に入れ、「フックがかかった状態」にしておくことです。
何となくリンクが付いているような状態で頭の片隅に残しておけば、いずれ頭の中を「検索すれば」わかるからです。
そうするためにも、何かを読んで知識を得た時、適度に忘れていくことが大事なのだと思います。
多読のために必須なのは、「今読まなくてもいい本」を見抜く力かもしれません。
購入した本を4〜5ページ読んで、ピンとこない、あるいは今はフィットしないと感じたら、その本はいったん、閉じてしまう。
そして、読まずにしばらく置いておく「積読」にしておくのも、一つの手です。
大事なのは、「読むなら今」という瞬間を逃されずに、「読む旬」をつかまえて読むことです。
本に書かれた細かい方法論に囚われず、発信者の「ビジョン」と「ミッション」という根っこのところをつかまえる訓練をしながら本を読むといいでしょう。
その上で時間軸を追い、人の動きを俯瞰する。
ミッションという熱で人を動かしていく過程を、絵巻のように俯瞰してみるという訓練です。
実践者としてリアリスティックに生きるには、教養が不可欠なのです。
テクノロジーの進化がかつてない次元で人間の能力を拡張する時代に重要性を増してくるのは、俯瞰の目で紡ぐ「ストーリーテリング」と「未来に対する仮説を立てる力」だと感じています。
新しい本と古い本を対比しながら読むと、新たな思考の取っ掛かりが見えてきます。
現代の日本を知るには、なにより「近代」をおさらいしておくべきでしょう。
今の仕組みの多くは明治初期に作られたものであり、我々は明治時代にできて戦後に更新された「近代」というシステムに乗っかって生きているからです。
加えて、日本人を動かす「空気」というものの実態をつかまえ、言語化できるところまで持っていければ、なおいいでしょう。
学術文庫と新書の違いについて、自分なりにこう考えています。
学術文庫=思想的なアーカイブ
新書=より一般的な教養を身につける手がかりになる本
『風姿花伝』は人類の一つの到達点という趣があります。
あえて普段の仕事とは関係ない分野の本で感性を磨くのも重要かもしれません。
そしてそれこそが、自分なりの教養にもつながっていくのではないでしょうか。
本を読む時に、年代や年齢といった時間軸を押さえることは、時代的なセンスを身につける上でけっこう重要なファクターだと感じます。
好きな人物の伝記を何冊も並べて読んでみると、新しい発見がいくつも出てきます。
その人がどんなエネルギー量で、それをどちらの方に振り向けて一生を駆け抜けたかがよく見えるのです。
■【実践】3個の行動ポイント
【1933-1】「いかにして問題をとくか」を読む
【1933-2】「失敗の本質」「ミカドの肖像」「日本的霊性」をセットで読む
【1933-3】「風姿花伝」を読む
■ひと言まとめ
※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】忘れる読書
【著者名】落合陽一 ・ 著者情報
【出版社】PHP研究所
【出版日】2022/10/27
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】読む力を身につけたいときに
【キーワード】読書術、教養、思考
【頁 数】240ページ
【目 次】
第1章 持続可能な教養
第2章 忘れるために、本を読む
第3章 本で思考のフレームを磨け
第4章 「較べ読み」で捉えるテクノロジーと世界
第5章 「日本」と我々を更新(アップデート)する読書
第6章 感性を磨く読書
第7章 読書で自分の「熱」を探せ
この本で、あなたは変わる!
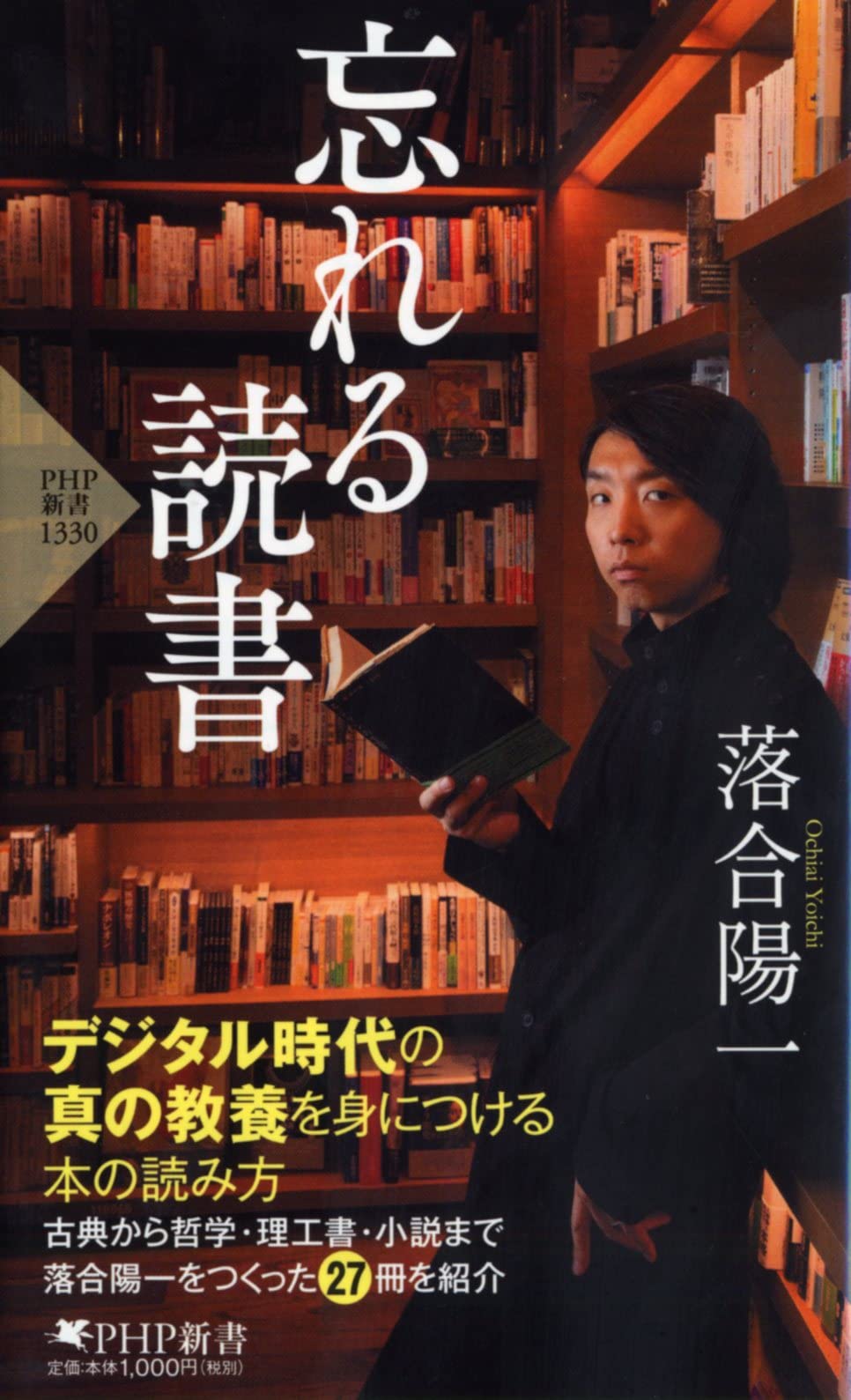
忘れる読書
落合陽一 PHP研究所 2022-10-27
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
落合陽一さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2022年 11月 10日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(10/31〜11/6)
-
2022年 11月 22日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(11/14〜11/20)
-
2022年 12月 02日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキング(2022年11月版)
-
2022年 12月 13日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(12/5〜12/11)
-
2023年 1月 10日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキングTOP10(1/2〜1/8)
-
2023年 1月 17日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキングTOP10(1/9〜1/15)
-
2023年 2月 05日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキングTOP10(2023年1月版)


この記事へのコメントはありません。