【これはおもしろい!ウソを手放せない人間の性】
脳科学者・中野信子氏が、『フェイク』と題して、「人はなぜウソをつくのか?」という疑問に脳内メカニズムからアプローチし、ウソに振り回されない知恵を考察する一冊。
■書籍の紹介文
ウソをつくとき。
それって、どんな気持ちのときですか?
本書は、脳の性質の観点からみると「人はウソに弱くできている」と指摘し、フェイクにまみれた世界を、ウソに振り回されない知恵を考察する一冊。
真実とフェイク、事実とウソ、一方の正義ともう一方の正義・・・・。
人間は、いつもフェイクに振り回されて、袋小路のなかでもがき苦しんでいます。
ではなぜ、苦しむ原因となるフェイクを、人間は手放せないのでしょうか。
それは、人間が人間であるために、フェイクが必要だからです。
こう聞くと「?」が浮かぶとおもいます。
ぜひ、その「なに言っているの?」というおもいを大切にしながら、読んでみてください。
「?」が解消されるにつれ、爽快感をおぼえます。
読み物としても、教養物としても、とてもおもしろい一冊です。
なぜ、人類の進化に”フェイク”が登場したのか。
なぜ、弊害をもたらす”フェイク”を人類は手放せないのか。
なぜ、”フェイク”を触媒にすることで社会が保たれるのか。
脳科学はもとより、人類の進化論にも通ずる話は、読む手が止まらなくなります。
”フェイク”に振り回さないための視座を得るためにも、一読の価値は高いとおもいます。
”フェイク”には、”悪”と”善”の両面があります。
両面にあることを理解して、”フェイク”の闇に引きずり込まれない知恵を身につけましょう。
◆これは良書。
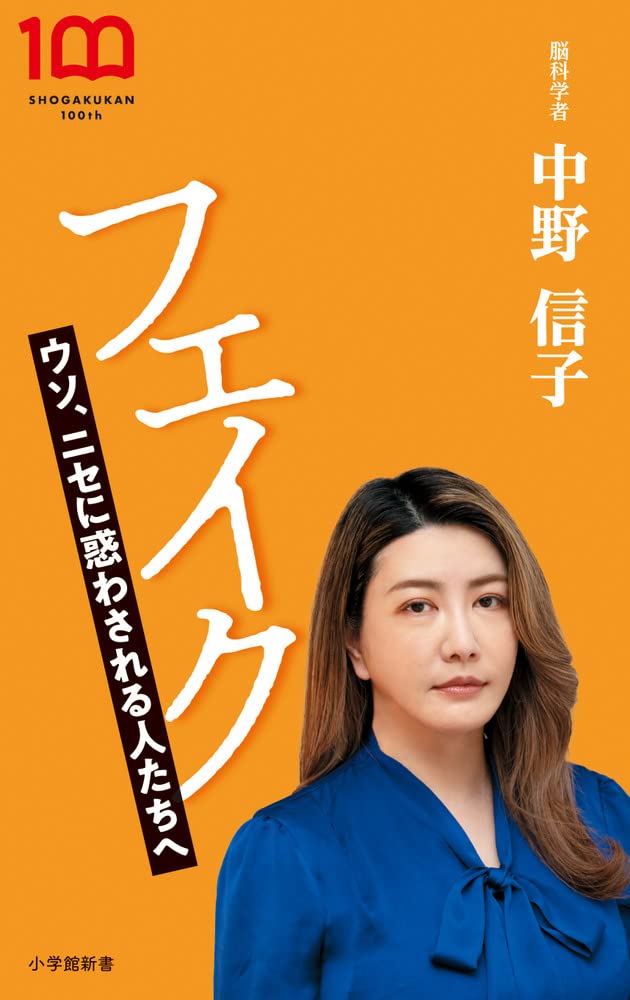
フェイク
中野信子 小学館 2022-6-1
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
もしウソが人間にとって本当に「よくないこと」「不要なもの」であったのならば、この能力はとっくに退化して消失していることでしょう。
人間はむしろ積極的に、ポジティブにウソを利用しながら、集団を保持し、人間関係を構築してきたとも言えるのです。
「あいつは敵だ」「敵は悪である」「正義は我々にある」「敵は弱い」「必ず勝てる」
こうしたウソには、期待や可能性を抱かせる役割があり、それによって、脳が快感の報酬を得る仕組みになっています。
だからこそ、使うためにはセンスも必要ですし、よく吟味して適用することが求められます。
大きな危険性を孕んでいるものだからです。
人間の性質を把握し、人々を扇動しようとする人に利用されてしまうことがあるので、注意が必要なのです。
事実を正確に知る方法をもっておくということは、リスクヘッジに不可欠です。
自分が知りえた情報から、「それが事実なのか」「事実と信じてよいのか」「リスクはないか」などと正しい意思決定を行うためにしっかりと確認する方法を身に付け、少なくとも安易に信じないという姿勢を大切にすべきです。
人は自分の願望に合致した情報だけを選択しようとし、都合の悪い情報は無視したり、軽視したりする性質をもっている。
そこには注意すべきときもあれば、上手に活用すべき場合もある。
そう知っておくことは生きる上で役に立つこともあるでしょう。
ウソという概念を完全に否定し排除するのではなく、有益なウソと悪意のウソがあるということを知り、ウソに対する目利きができるようになると、人生はより生きやすいはずです。
そしてそれこそが社会性を身に付けることでもあるのではないでしょうか。
人間は個人の意思決定が強い。
それでも、異なる互いの個人の意思決定の基準をぶつけ合いながら、社会を形成し、共同体をつくらなければなりません。
しかしあまりにも強くぶつかりすぎると、共同体そのものが崩壊してしまうこともあります。
だから個人を細胞とするならば、細胞と細胞の間を埋めるための、間質というか、細胞と細胞を結合させるための接着分子としてのフェイクが存在するのではないかと思うのです。
ウソが苦手な人は、普段から、話術がたくみな人(大体はウソつきです)の言葉で、「ウソだとは思うけどいいな」「これは使えるな」と感じるような言い回しを覚え、ストックしておくとよいでしょう。
SNSの危険なところは、自分が知らず知らずのうちに、誰かに誘導された選択肢を選び、いらぬトラブルに巻き込まれてしまうことです。
自分が気を付けていても、自分が情報を預けた先で何が起こるか、まったく予測できないのです。
企業の不正がなぜなくならないのかと言えば、共同体によってそれぞれの基準がある以上、片方から見れば不正であり、片方から見ると不正ではないという事象が生じてしまうからです。
「ブルーベリーが目によい」という説は、イギリスが第二次世界大戦で発信されたあるウソが元になっていると言われています。
真理探究が目的であり、誠実であるべき学術論文がウソとして発信されることもあります。
そのフェイクが何を目的に、どうなることを想定して作られたのかと思考する。
自分からエビデンスを集める努力をしないような人は標的にされてしまいます。
明示的に表現できない何となくの感覚であっても、嫌な予感がする人とは、適度な距離感を保ち、相手が自分に対してアグレッシブな態度をとった場合にはどういう対応をとるかなど、準備をしておくべきです。
フェイクニュース=ウソに騙されないためには、まず日頃から信頼できるメディアを複数チェックし、同じ事象について、情報を比較確認するということが重要です。
■【実践】3個の行動ポイント
【1863-1】「騙されない人間はいない」ということを常に意識する
【1863-2】「おかしいかも?」など、自分の直感を大切にする
【1863-3】信頼できるメディアを複数持っておく
■ひと言まとめ
※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】フェイク
【著者名】中野信子 ・ 著者情報
【出版社】小学館
【出版日】2022/6/1
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】明日の人間関係を良くしたいときに
【キーワード】教養、脳科学、人間関係
【頁 数】192ページ
【目 次】
第一章 何のために人はウソをつくのか
第二章 人はなぜ騙されるのか?
第三章 社会性とウソ
第四章 生産的ウソの効用と活用法
第五章 悪意のあるウソ
第六章 歴史から見るフェイクの活用例
第七章 ウソとどう付き合い、生きていくのか
この本で、あなたは変わる!
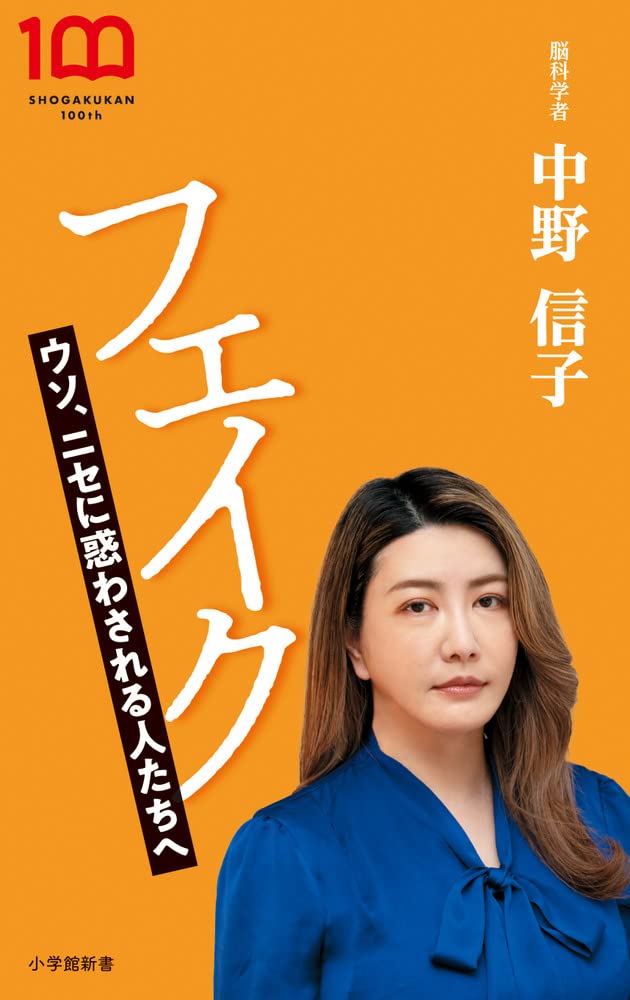
フェイク
中野信子 小学館 2022-6-1
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
中野信子さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)
■お知らせ
▼「いいね!」応援をありがとうございます!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2022年 6月 16日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(6/6〜6/12)
-
2022年 7月 25日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(7/18〜7/24)

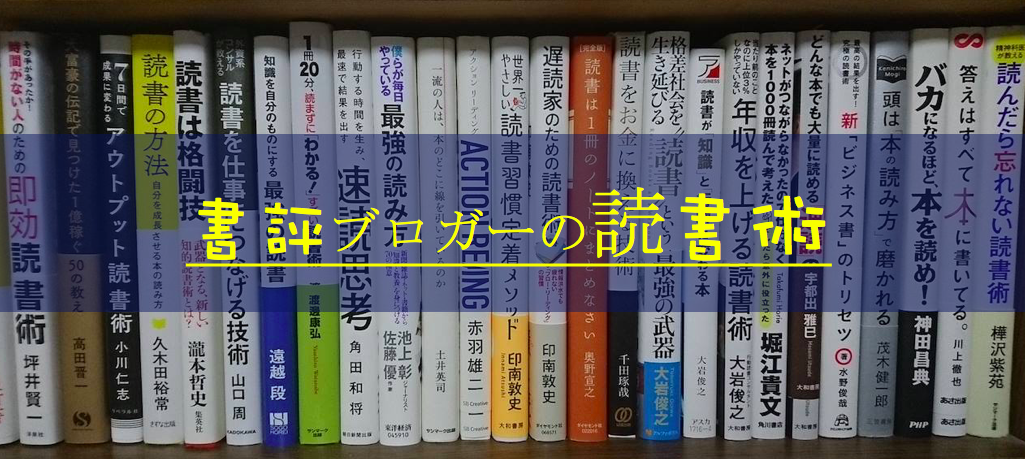


この記事へのコメントはありません。