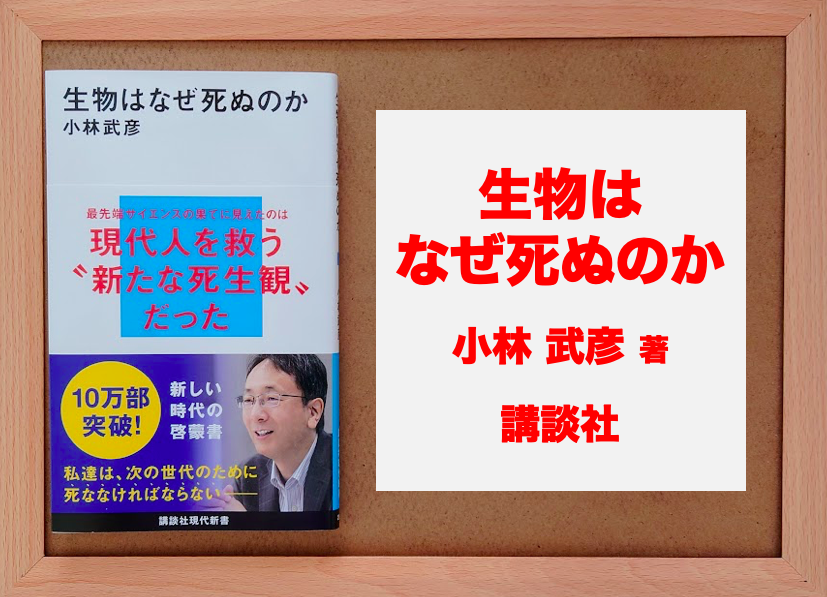
【次の世代のために、どう生きどう死ぬか】
生物学者・小林武彦氏が、『生物はなぜ死ぬのか』と題して、すべての生命の死には重要な意味があると提起し、なぜ遺伝子には「死」がプログラムされているのかを考察する一冊。
■書籍の紹介文
生命はなぜ死ぬのでしょうか。
じっくり考えたことはありますか?
本書は、なぜ地球に生命が溢れているのか、そして生命はなぜ死ぬのかを生物学の視点から紐解きながら、われわれの遺伝子に「死」がプログラムされている意味を考察する一冊。
この本はとにかくおもしろい!
ぜひ、ぜひとも、読んでいただきたいとおもいます。
『生まれてくるのは「偶然」だが、死ぬのは「必然」である。』
グッと惹きつけるこの一節に込められている”生物学的教養”に触れることで、自分の生き方を見つめ直そうとするいろいろな扉が開く感覚を覚えます。
考察を展開する”構成”と著者の”語り口”のさじ加減が絶妙。
予備知識に自信がない方でも、安心して読むことができます。
地球に生命が誕生するまでの壮大かつ奇跡的なドラマ。
そこから現代に至るまでに、生物はヒトはどのような進化を遂げてきたのか。
そして今、気候変動などの影響により種の大量絶滅時代に突入したと言われる地球環境。
人間社会ではついに、ヒトとは違って決して”死ぬことのないAI”を誕生させました。
いったい生命はこれからどう進化するのか、われわれ人間の未来はどうなっていくのか。
そこに、生命にプログラミングされている「死」はどう関わっていくのか。
たぶんに哲学的な要素も含まれており、知的好奇心をグイグイと刺激されます。
日頃、近視眼的な思考になりがちなわたし達の、視野を広げてくれる善きガイドとなることでしょう。
「生物はなぜ死ぬのか」の理由を知ること。
それにより、主体的に生きることを考えるようになっていきます。
◆これは必読の良書!
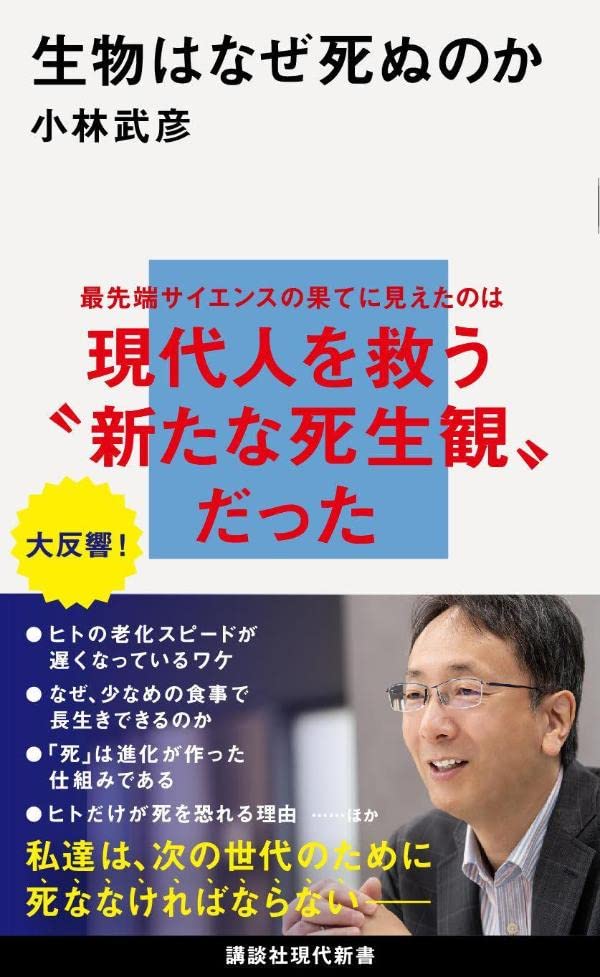
生物はなぜ死ぬのか
小林武彦 講談社 2021-4-14
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
生命のことを知るためには、宇宙誕生の歴史を切り離して考えることはできないのです。
なぜ地球で生物が誕生したかは、今でもわかっていません。
生命誕生の瞬間を実際に見た人はいないし、再現実験で人工的に生物を作ることにもまだ成功していないので、想像するしかありませんね。
生物と無生物の大きな違いは、単独で存在でき、それ自身で増えることができるかどうかです。
化学反応が頻発する可能性に満ちた原始の地球で、何億年という長い年月をかけて、低い確率、というか偶然、というか奇跡、が積み重なりました。
そして何よりも、生産性と保存性の高いものが生き残る「正のスパイラル」が、限られた空間で常に起こり続けることで、偶然が必然となり、生命が誕生したのです。
ターンオーバー(turn over/生まれ変わり)こそが奇跡の星地球の最大の魅力です。
そしてその生まれ変わりを支えているのは、新しく生まれることとともに、綺麗に散ることです。
この「散る=死ぬ」ということが、新しい生命を育み地球の美しさを支えているのです。
現在進行中の絶滅の時代も、同様に新しい地球環境に適応した新種が現れて、地球の新しい秩序ができ上がっていくのでしょう。
ただこれは数百万年もかかる変化で、私たちの子孫がそこにいるかどうかも、わかりません。
「多様化ー絶滅」の関係、言い換えれば「変化ー選択」のサイクルのおかげで、私たちも含めた現存の生き物が結果的に誕生し、存在しているのです。
これはつまり、ターンオーバーに次ぐ、本書の2つ目のポイントである「進化が生き物を作った」ということですね。
生物を作り上げた進化は、実は<絶滅=死>によってもたらされたものです。
小さい生き物は逃げること、つまり「(他の生き物から)食べられないことが生きること」、一方、比較的大きな生き物は自分の体を維持するために、「食べることが生きること」ということになります。
生き物が誕生してから、長い時間をかけて多様化してきましたが、多様化したのは形態や生態だけではありません。
その生きざまに応じて死に方も多様化し、進化してきたのです。
生き物によって違いはありますが、このような死に方は、生き残るために進化していく過程で「選択された」ものだということは共通しています。
つまり、いま生き残っている生き物たちにおいては、その「死に方」でさえも何らかの意味があったからこそ、存在しているはずなのです。
現代人の死に方は、アクシデントで死ぬ、あるいは昆虫や魚のようにプログラムされた寿命できっちり死ぬのとは違い、「老化」の過程で死にます。
老化は細胞レベルで起こる不可逆的、つまり後戻りできない「生理現象」で、細胞の機能が徐々に低下し、分裂しなくなり、やがて死に至ります。
細胞老化には、活性酸素や変異の蓄積により異常になりそうな細胞を異常になる前にあらかじめ排除し、新しい細胞と入れ替えるという非常に重要な働きがあるのです。
これによって、がん化のリスクを抑えているのです。
なぜ、テロメア合成酵素の働きをわざわざ止めて老化を誘導するという勿体無いことをするのかーーーこの問いに対する答えは、ここにありました。
老化が死を引き起こすというのは、生き物の中でも特にヒトに特徴的ですが、「進化が生き物を作った」とすれば、老化もまた、ヒトが長い歴史の中で「生きるために獲得してきたもの」と言えるのです。
食う、食われる、そして世代交代による生と死の繰り返しは、生物の多様性を促し、生物界のロバストネス(頑強性、安定性)を増しています。
つまり生き物にとっての「死」は、子供を産むことと同じくらい自然な、しかも必然的なものなのです。
死は生命の連続性を維持する原動力なのです。
ヒトには寿命があり、いずれ死にます。
そして、世代を経てゆっくりと変化していくーーーそれをいつも主体的に繰り返してきましたし、これからもそうあることで、存在し続けていけるのです。
■【実践】3個の行動ポイント
【2044-1】多様であることを大切にする
【2044-2】変化することを積極的に楽しむ
【2044-3】いろいろな経験をして、たくさん共感することを大切にする
■ひと言まとめ
※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】生物はなぜ死ぬのか
【著者名】小林武彦 ・ 著者情報
【出版社】講談社
【出版日】2021/4/14
【オススメ度】★★★★★
【こんな時に】生き方に迷ったときに
【キーワード】サイエンス、教養、哲学
【頁 数】224ページ
【目 次】
第1章 そもそも生物はなぜ誕生したのか
第2章 そもそも生物はなぜ絶滅するのか
第3章 そもそも生物はどのように死ぬのか
第4章 そもそもヒトはどのように死ぬのか
第5章 そもそも生物はなぜ死ぬのか
▼さっそくこの本を読む
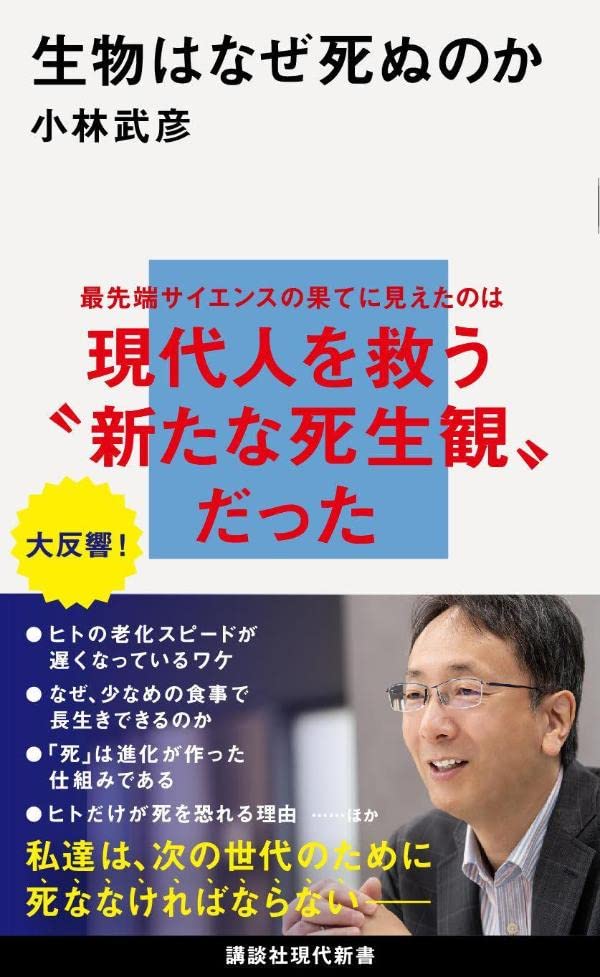
生物はなぜ死ぬのか
小林武彦 講談社 2021-4-14
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
小林武彦さん、素敵な一冊をありがとうございました!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2023年 8月 16日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキングTOP10(8/7〜8/13)
-
2023年 9月 04日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキングTOP10(2023年8月版)


この記事へのコメントはありません。