- 2020-1-21
- 本のシェア
- CCCメディアハウス, ★★★☆☆, マインド, 信用残高, 働き方, 栗下直也, 生き方に迷ったときに
- コメントを書く
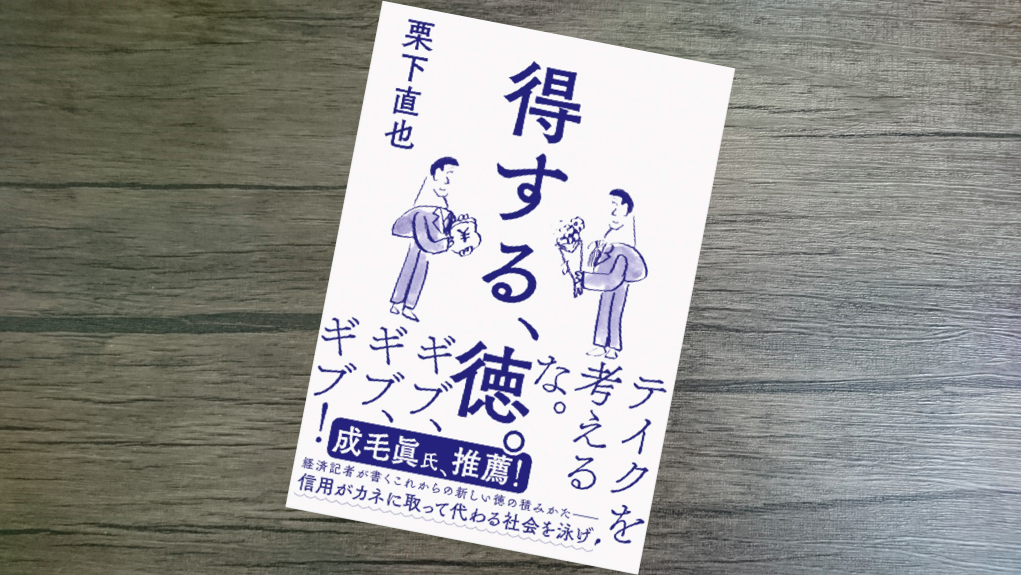
【通貨は、貨幣から信用の時代へ】
経済記者・栗下直也氏が、『得する、徳。』と題して、昨今注目される”信用”を読み解くヒントは”徳を積む”行為にあると提起し、時代の流れに即した徳を積む方法を考察する一冊。
もくじ
■書籍の紹介文
徳を積む。
どんな行為をイメージしますか?
本書は、日本に昔からある「徳を積む行為」とテクノロジーが実現する「信用の見える化」を融合させた、現代版の”徳を積む方法”を考察する一冊。
昨今、議論が盛んになっている『信用』。
信用の”見える化”や信用の”ポイント化”による、”信用経済”という言葉が最たるものでしょう。
しかし、『信用』はなにも突然出てきたものではありません。
歴史を紐解いていけば、人間社会は『信用』によって成り立ってきたことは自明です。
それが、行き過ぎた資本主義の蔓延によって、忘れるほど隅に追いやられていた。
そして、行き過ぎによる社会経済の歪みや新しいテクノロジーの出現で、今また『信用』の存在を思い出しつつある。
これが、今の世界の潮流です。
利益重視の資本主義社会に、どうやって信用重視の社会をミックスしていくかを考える過渡期というわけです。
著者は、この状況は、日本人にとって個人にも企業にも大きなチャンス到来だと指摘します。
なぜなら、「徳を積む」という言葉が昔からあるように、信用を重視した社会は日本人には特に馴染み深いシステムだからです。
罪を認めたのだから裁判に出るという信用を裏切って、逃走をする不届き者。
困っていると分かっているのに、見て見ぬ振りをする者ばかりの公共の空間。
信用に馴染み深い日本人でも、リハビリに必要な人が大勢いるのが現状です。
だからこそ、いち早く「徳を積む」ことを喜びにできると、将来の得につながる可能性が大きくなるのです。
「徳を積む」とは、困っている人を助けること。
本書で思考のリハビリをしながら、さっそく困っている人を助けましょう!
◆徳を積むことで、得に換わる。
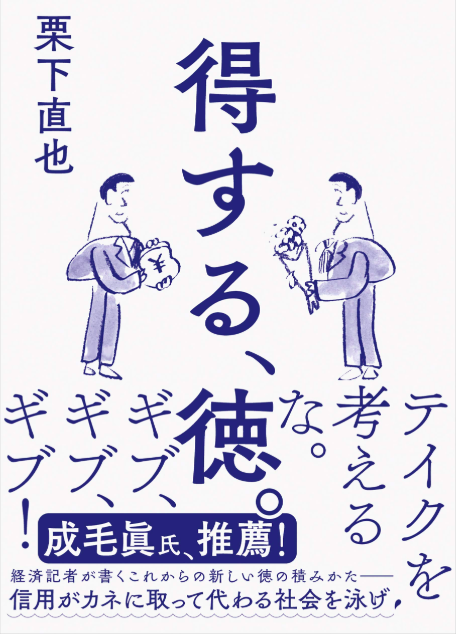
得する、徳。
栗下直也 CCCメディアハウス 2019-12-21
売上ランキング(公開時):63,861
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
目先の利益だけに飛びつくヤツは、いずれ淘汰されるものだ。
長期的に考えれば、目先の損得の収支で判断することが賢明とは決して言えない。
徳をうまく積むことは幸せにつながるのだ。
(アダム・グラントの『GIVE&TAKE』(書評はコチラ)では)「成功ピラミッドの最上位を占めるのは、自分の利 益を優先せず、惜しみなく人に与える人間だ」と示した。
全米はひっくり返ったが、日本人からすれば「やっぱりね」という感じだ。
堀江貴文氏は、「信用こそビジネスや仕事を進める上で重要だ」とあらゆる書籍で強調している。
彼は「カネよりも信用が大事だ。信用のためにカネを使うべきだ。信用があれば生きていける」と語る。
個人がお金の代わりになる信用を創る「信用主義経済」に向けた動きは既に起きている。
いざという時、お金に頼らず生きていける人同士のネットワークが築ければ、タダ同然で生きていける。
●「与え続ける人」になるために注意すべきこと
(1)何もかもは引き受けない
(2)無理に「いい人」を目指さない
(3)利己的すぎる人間から距離を置く
「SDGs」とは、貧困撲滅や気候変動への対応、水の安全や健康福祉など「持続可能な世界の実現」に向けて、国連が定めた17の目標のことだ。
「SDGs」を戦略の中心に据えることを、企業のこれからのあるべき姿だとする機運が高まっている。
ビジネスを通じて、社会課題を解決する視点を多くの企業が持ちはじめているのだ。
企業はどうあるべきかを考える時、「株主は、短期的に自己の利益を追求するためにだけ議決権を行使すべきだ」という根拠は揺らいでいる。
そのことはもっと知られるべきだ。
個人だけでなく、組織も利他性なくして生き残れない時代だ。
それは「会社の一員」であり「会社と取引がある個人」にも「与える」姿勢が求められてくることを意味するのだ。
徳を積むことを難しく考える必要はない。
重要なことは、目先の利益に惑わされず「まず与える」気持ちを持つことだ。
確かに、徳を積むには、多少の労力と時間が必要だ。
無理は禁物だ。
できる範囲でいい。
「徳」を積めば、カネは後からついてくる。
徳は、忘れた頃に「得」になるものなのだ。
気が向かなくても続けていれば、自然に積めるようになるはずだ。
当たり前のことだが、これまではカネがなければ生きていけなかった。
ところが昨今は、ソーシャルメディアの中に「奢られる」プロや「何もしない」プロが出現している。
信用を貯めて、信用を使うのだ。
ネットの発達やデータ活用が拡大したことで、信用の換金化はこれからますます積極的に推進されていくはずだ。
他者が信じられないからシステムで縛るのか、それとも、与え、与えられる関係をベースにした社会を構築するのか。
私達は、今その分岐点にいるのだ。
身近な人の行動が、周りの人を変えるのだ。
だから、とりあえず、自分が動くことだ。
最初は外発的理由でも、徳を積み続ければ、いつの間にか徳を積むことが喜びに変わるはずだ。
■【実践】3個の行動ポイント
【1599-1】「与える」ことを意識して行動する
【1599-2】「信用が貯まるかどうか」を行動の判断軸にする
【1599-3】「SDGs」にアンテナを貼る
■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】得する、徳。
【著者名】栗下直也 ・ 著者情報
【出版社】CCCメディアハウス
【出版日】2019/12/21
【オススメ度】★★★☆☆
【こんな時に】生き方に迷ったときに
【キーワード】信用残高、働き方、マインド
【頁 数】224ページ
【目 次】
第1章 信用社会の到来
第2章 偉人の「徳」に学ぶ
第3章 会社は誰のモノなのか
第4章 なんのために働くのか
この本が、あなたを変える!
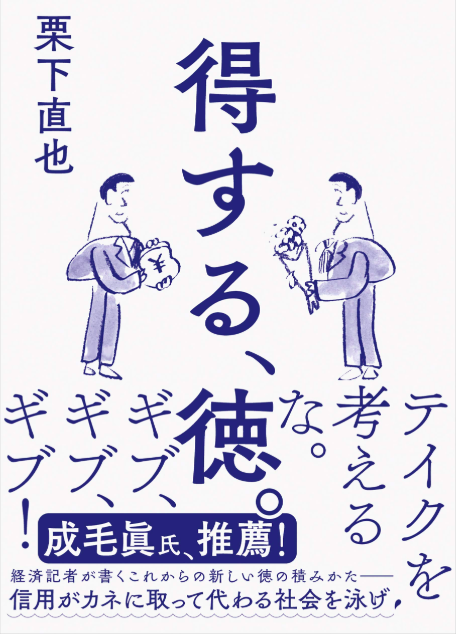
得する、徳。
栗下直也 CCCメディアハウス 2019-12-21
売上ランキング(公開時):63,861
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
栗下直也さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)
■お知らせ
▼【聴いてね♪】書評ラジオ番組
「米山智裕のBook of the Week」
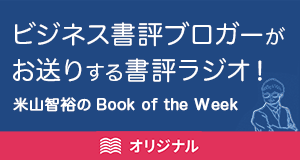
▼「いいね!」応援をありがとうございます!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
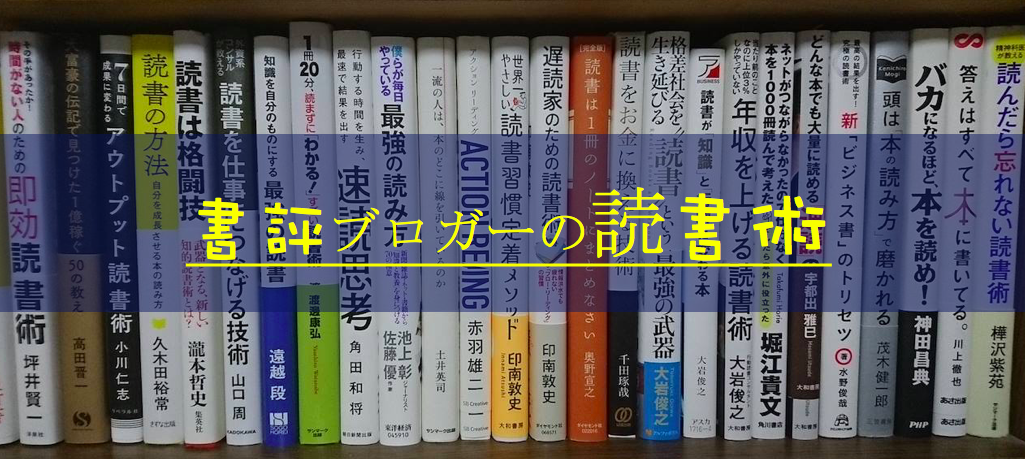

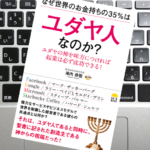
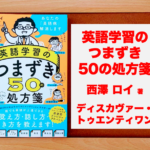
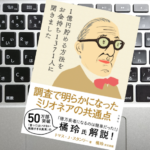
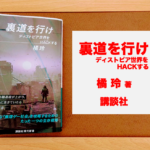
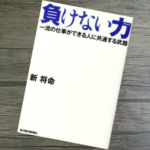
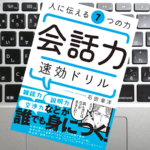
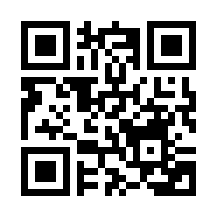
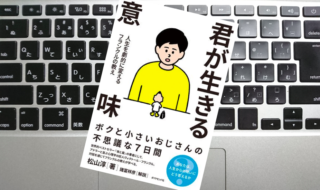



この記事へのコメントはありません。