【日本の根底を流れる、禅の空気】
曹洞宗徳雄山建功寺住職・枡野俊明氏が、日本の文化、芸術、芸能の確たる源流に禅があるとし、人生を整える禅的考え方の基本を説く一冊。禅を活かすには、基本を学ぶことが大事。
■この本の紹介文
毎日さまざまな刺激を受ける心。
じぶんの心を整える方法を持っていますか?
本書は、人生を整えるものである「禅」の教え、考え方を、臨機応変に自在に活かすことができるようになるための基本に焦点をあててまとめ上げた一冊。
・侘び茶を完成させた「千利休」
・能に通じる猿楽を完成させた「世阿弥」
・日本を代表する墨絵作家「雪舟」
いずれも禅僧であったことを、あなたは知っていますか?
このように、日本の文化、芸術、芸能の確たる源流には「禅」があります。
だからこそ、禅を知ることは、日本を知ることに繋がっているのです。
この本は、禅を大きく捉えて基本が学べるようになっています。
日本人として、押さえておきたい教養が、ここにあります。
◆禅の道の一歩を、この本から!
■本がわかる!15の要約ポイント
何かを得るためにすわるのでもなければ、何者かになるためにすわるのでもないのです。
すわることそれ自体に一心に打ち込む、全身全霊を傾ける。
それが坐禅です。
一つ気づくことは、小さな悟りを得ることといっていいかもしれません。
大切なのは、願い、努力した「結果」をそのまま受け容れることです。
禅はどうにもならないことは、そのまま受け容れなさい、と教えます。
死はまさにその象徴的なものです。
修行僧はどのような一日を送るべきか、それがこまかく記されているのが「清規(しんぎ)」と呼ばれるものです。
修行生活のなかでいちばんつらいのは何だと思いますか。
じつは空腹、ひもじさなのです。
質素、少量。
それが空腹感をもたらす二大要因だと思いますが、修行中の食事は極限のそれです。
仲間の存在の大切さ、仲間がいることのありがたさ。
そのことも修行を通して体感します。
仲間がいなければ修行は続けていけない。
坐禅三昧、作務三昧、読経三昧……。
人は一度にたった一つのことにしか無心で打ち込むことはできません。
「ながら」では絶対にそれができないのです。
いまなすべきことは、いまの心でなければ、見えてきません。
いつでもいまの心をはたらかせ、なすべきことをきちんと見据えてしっかりとやっていく。
それが禅です。
禅では、人は一人ひとりが絶対の存在だと考えます。
誰もが余人をもって代えがたい自分なのです。
そのことをしっかり認識することが大切です。
何にもとらわれず、こだわらず、自在に変化しながら、自分を失うことがない。
そこに真の自由があります。
禅とはきってもきれない関係にあるのが「日本文化」です。
茶道、華道、書道など、日本の伝統文化には「道」のつくものが多くあります。
それらはどれも、禅の影響を受けているといっても、けっして過言ではありません。
喧噪のなかにいても、心は静けさのなかにある。
それが禅の静寂です。
「善因善果」「悪因悪果」は必然。
それが禅の考え方です。
春夏秋冬、それぞれの1日、「禅の庭」に立ってみませんか。
そして、その佇まいから漂ってくるものを身体いっぱいに感じてください。
それはそのまま禅の世界を体感することです。
■これをやろう!3つの実践ポイント
【1113-1】自宅周辺にある禅寺を調べる
【1113-2】興味の湧いた禅寺を訪れてみる
【1113-3】この本をくり返し読む
■ひと言まとめ
禅を学ぶことは、心を学ぶこと
【書籍名】人生を整える 禅的考え方
【著者名】枡野俊明
【出版社】大和書房
【出版日】2017/11/23
【オススメ度】★★★★★
【こんな時に】心の平穏や導きがほしいときに
【キーワード】禅、教養、哲学
【頁 数】240ページ
【目 次】
第一章 禅と悟り
第二章 禅と修行
第三章 禅と心
第四章 禅
この本で、あなたは変わる!
枡野俊明さん、素敵な一冊をありがとうございます\(^o^)/
■お知らせ
▼【聴いてね♪】書評ラジオ番組
「米山智裕のBook of the Week」
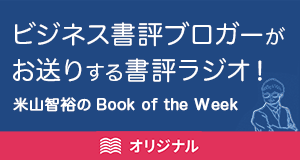
▼「いいね!」応援をありがとうございます!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2018年 1月 30日
-
2018年 2月 11日

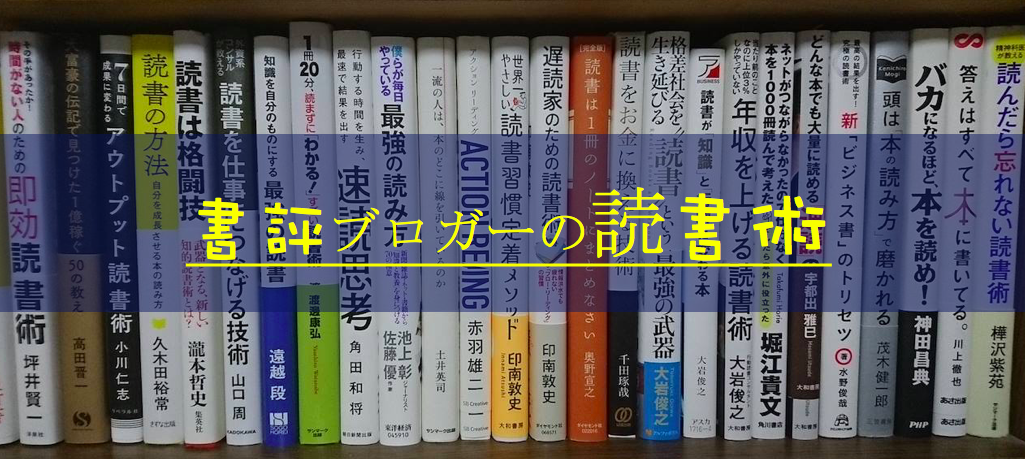

この記事へのコメントはありません。