- 2016-7-7
- 本のシェア
- ★★★★☆, キャリアアップ, ディスカヴァー・トゥエンティワン, 小宮一慶, 教養, 数学的思考, 考える力を身につけたいときに
- コメントを書く
【数字は思考のスタート地点!】経営コンサルタント・小宮一慶氏が、世の中の動きや未来は「数字」で読み解くことができると説き、「数字力」を養成する講座を開講。ビジネスマンのための最新講座は全員必修です!
===================
■1分間紹介文
===================
「GDPが前年比◯%の上昇でした。」と流れるニュース。
それを見て、「ふ〜ん、そうなんだ。実感ないな」とだけつぶやきチャンネルを回す。
もしあなたが、数字の情報をただ流してしまっているなら、この本を読みたい。
著者は、小宮一慶さん。
経営コンサルタント。
株式会社小宮コンサルタンツ代表。企業規模、業種を超えた「経営の原理原則」を元に、幅広く経営コンサルティング活動を行う一方、年100回以上講演を行う。日経新聞の景気指標を用いた講演は定評がある。
本書は、「数字」こそ世の中の動きやこれからの未来を読み解くキーがあると説き、その「数字力」を磨くための方法を紹介した一冊。「基本的な数字」と「基礎的な知識」を軸に、あなたの世の中を見る目を広く深くしてくれる。
・日本の人口は何人ですか?
・日本の労働力人口は何人ですか?
・日本のGDP総額はいくらですか?
・世界のGDP総額はいくらで日本のシェアは何%ですか?
さて、あなたはスラスラと回答できるだろうか。(答えは本書を!)
数字はブレない。
数字を軸に考えることで、全体像をイメージしたり、具体化したり、今後を推理したり、数字同士を関連づけたり、目標達成までの目安にしたりと、その思考の範囲は無限大である。
結果、数字を見ることができる人は、物事の見方や達成度が、数字を意識しない人に比べて大きく異なってくるのだ。
難しく考えずにぜひ読んでみてほしい。
読み進めて、ポイントポイントのワークをやっていくうちに、だんだん数字を使って考えることの意味がわかってくる。それと並行して、じわじわと楽しくなる感覚が味わえることを約束する。
まずは、あなたの給与明細を用意。
そこに並ぶ数字を本書のエッセンスを絡めて読むと、世の中のいろいろなことがわかります。
そして、なぜその金額なのかもわかってきます。
数字はすべての思考のスタート地点!
数字を抜きには考えたとは言えないのだ。
===================
■本のエッセンスがわかる15のポイント
===================
●数字力を高めるステップ
ステップ1:数字を具体的に把握する(数字とその定義や意味することを知る)
ステップ2:数字と数字を関連づける
ステップ3:数字を自分でコントロールし、つくっていく
ニュースを見て、あれ?なぜ?と思ったら、数字を確認してみる。
数字を見たら、その裏を推理してみる。
この習慣が大事です。それによって、世界がどんどん深く見えてきます。
自分の身の回りの数字を確認する習慣を持つことも大切です。
来月、給与明細をもらったら、社会保険料を確認してください。手取り額や残業代だけでなく、税金や社会保険料も確認することです。
基本的な数字を知っておく、これは、「数字力の基本」のもっともベースになります。
基本的な数字には、GDPや国家予算などのマクロの数字、いわゆる「経済」の数字と、決算書に代表されるような「会計」の数字があります
GDPの定義を知り、数字間の関連が分かれば、この先の予測を立てやすいということです。そのためにも、GDPの定義などの「基礎的な知識」が必要なのです。
世界のGDPは、だいたいいくらぐらいなのでしょうか。ご存じですか?
答えは、72兆ドル(こちらは、IMFが発表しているデータによります)。
ここまで、お読みいただいた読者の方には、72兆ドル、と聞いて、「そ
うなんだ」で終わってしまわれては困ります。「ということは……」と、瞬間的にいろいろと考えを巡らせていなければいけません。
基本的な数字は、生ものですからコンスタントに更新していかなければ役に立たないのに対し、基礎的な知識は、一度覚えたらほぼ一生使えます。
①貸借対照表では、会社の安全性を見ます。
②損益計算書では、会社が会計上いくら儲かっているかを見ます。
③キャッシュ・フォロー計算書では、現実のお金の流れ(どこで増えて、どこで減っているのか)を見ます。
貸借対照表や損益計算書の基礎的な知識をもっと多くの人が知って、新国立競技場だけではない、税金のさまざまな杜撰な使われ方を監視し、声を上げていったら、国の財政ももっと健全になるのではないでしょうか?
●「数字の見方」4つの基本
①重要な数字とその定義を知っておく。
②全体の数字の中での位置づけを知る。
③統計的に考える。
④数字と数字を関連づけ、「仮説」を立てる。
統計では、「平均値(算術平均)」と「中央値」と「最頻値」三つがあります。ときどき不適切な値を用いているデータもありますので、数値を見たとき、どの値を使っているのかを確認することが重要です。
「みんな」とか「ほとんど」という表現が出てきたら要注意。それは何人中何人なのか、全体はいくつで、その中のいくつについて調べて、その結果いくつなのか、説明してもらう必要があります。そういう習慣づけが「数字力」強化、ひいては目標達成力向上につながるのです。
わたしは数字の訓練として、月曜日の日経新聞の「景気指標」欄に必ず目を通します。
「基礎的な知識」については、週に一時間でもけっこうですから、別の時間をとって勉強する習慣をつけたいものです。ずっと理解力が高まり続けます。
===================
■これをやってみよう!3つの実践ポイント
===================
【761-1】「基本的な数字」を常に把握する
【761-2】ニュースで数字を見たら、「ということは?」と投げかける習慣をつける
【761-3】「基礎的な知識」を週に1時間勉強する習慣をつくる
===================
■今回のまとめ
===================
数字はすべての思考のスタート地点!
===================
■本日紹介した書籍情報
===================
【書籍名】ビジネスマンのための最新「数字力」養成講座
【著者名】小宮一慶
【出版社】ディスカヴァー・トゥエンティワン
【出版日】2016/6/16
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】考える力を身につけたいときに
【キーワード】数学的思考、教養、キャリアアップ
【頁 数】240ページ
【目 次】
第一章 数字が見えると、世の中が見える
第二章 基本的な経済の数字と定義を知る
第三章 基本的な「会計」の数字と定義を知る
第四章 「数字」の見方 四つの基本
第五章 「数字力」を鍛える11の習慣
小宮一慶さん、素敵な一冊をありがとうございます\(^o^)/
< span style="font-size: 12pt;">本日もお読みいただきありがとうございました!
■【読者登録受付中】メルマガの配信を開始しました!■
登録はこちらから
※注意※
PCアドレスでの登録にご協力をお願いします。
携帯アドレスだと届かないことがございます。
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
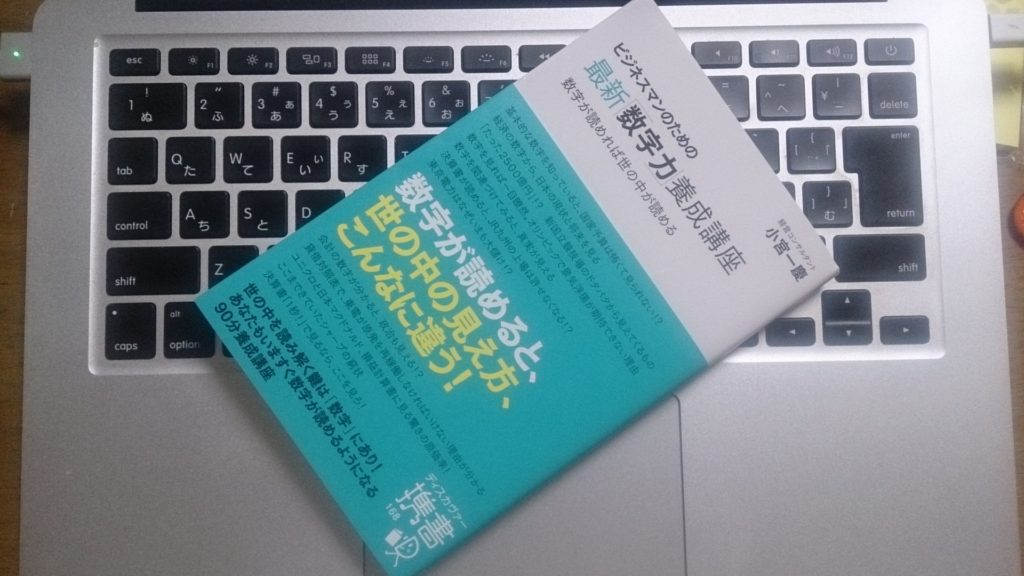
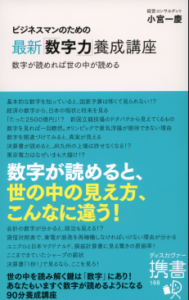

この記事へのコメントはありません。