
【読解力の高低は人生の質に直結する!】
伝える力研究所所長・山口拓朗氏が、『読解力は最強の知性である』と題して、人生を好転させたければ読解力を高めることだと提起し、正しく読解力を高めていく方法を指南する一冊。
■書籍の紹介文
物事の本質を見抜く「読解力」。
あなたは自分の「読解力」に自信を持てていますか?
本書は、「読解力とはわたし達の人生を支えているOSのようなもの」だと提起し、高い読解力を持つ人の能力を紐解きながら、正しく読解力を高めていく方法を指南する一冊。
読解力とは
言葉や文章、あるいはその場の空気や雰囲気、特定の事象について、その内容を正確に理解・解釈する力のこと。
単純に意味や事実を「把握する」だけではなく、その奥や裏にある”根本的な性質”までを「洞察する」。
この2つの能力を伸ばしてはじめて、「読解力を高めることができた」といえるのです。
言うまでもなく、わたしの時代は情報過多の時代です。
要不要に関わらず、大量の情報の波に翻弄されながら生きていく必要があります。
それ故、情報を見逃すまいというプレッシャーから、「把握する」ことに集中しがちです。
「お得な情報はないか」「知らないと損するかもしれない」と”強迫観念”に囚われたかの如く・・・。
こうなると、必然的に「洞察する」ことが疎かになってしまいます。
結果、話や情報の真意を見誤って手痛い失敗をしたり、騙されるなどして”情報弱者(情弱)”と揶揄されたりしてしまうわけです。
こんな悲しい事態にならないためには、『読解力を高めるほかない!』と著者は断言します。
そのうえで、そもそも読解力とは何か、どう学びどう磨いていけばいいのかを徹底的に指南していきます。
「無駄な部分が全くない」、そう圧倒されるほどに内容が凝縮されています。
本を読む→教えを実践する→本に立ち戻る、このサイクルを何度も回したくなる、”学びがい”のある素晴らしい一冊です。
もちろん、読解力を磨くことは、学んですぐに効果が出るほど生易しいものではありません。
だからこそ、信頼できる教えから学ぶことが大切になりますが、本書はその期待に応えてくれると直感できました。
読解力を磨いて、情報に惑わされることなく、物事の本質を理解できる人間になりたい。
但し、「理解できた」と満足してしまうことは”「理解したつもり」の罠”に陥る危険性を孕んでいる。
まったく、大切な教えであればあるほど、いつも矛盾を内包しているなとつくづく感じます。
一方で、矛盾を受け入れつつ、「読解力を磨くこと」と「理解・解釈できたつもりにならないこと」の間のバランスを見つけることが、本当の知性なのかなとおもいました。
腰を据えて学ぶ価値のある良書です。
◆かなりオススメな本!

読解力は最強の知性である
山口拓朗 SBクリエイティブ 2025-3-14
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
読解力が対象とするのは、文章だけとは限りません。
会話の内容や、対話する相手の気持ちを汲み取る力、さらには、その場の空気感、社会の潮流・潮目などを読み解くことまで含みます。
また、読解力では、「何を」「どこまで」読み解くか、ということも重要です。
●読解力の3要素
(1)本質読解:核心を読み解く
(2)表層読解:言葉を曲解することなく読み解く
(3)深層読解:言葉の裏や奥にある意図・真意・思惑・含みなどを読み解く
●読解力を高める5つの基本姿勢
(1)話の流れと論理を整理する
(2)質問を投げかける
(3)実際に体験する
(4)意見を交わす
(5)アップデートし続ける
読解力は、その人が「どれくらい言葉を知っているか」という点と深く関わっているわけです。
読解力を高めたいなら、知らない言葉に遭遇した際、手元のスマホを使い、その場ですぐに意味を調べる習慣をつけましょう。
読書を通じての語彙力強化は、読解力を高めるうえで最も効果的なアプローチです。
●『本質』を構成する3つの要素
①普遍的(時代や場所を超えて、変わらない特性や価値があるもの)
②汎用的(さまざまな用途に広く使えること)
③シンプル(ムダなところがなく簡素なさま)
本質にたどり着くために有効な2つの「問い」を提案します。
(1)なぜ
(2)そもそも
「なぜ」と「そもそも」、この2つの問いによって導き出される答えは、限りなく「本質」に近いものです。
どちらの「問い」も、その事柄の本質に近づくためのものですが、そのニュアンスは少し異なります。
・なぜ:理由や原因、動機などを突き止めるときに使う
・そもそも:背景や前提、定義、目的、事実などを明確にするときに使う
その文章を読み解き、本質に迫るためには、読む人自身が文章と積極的に関わらなければいけません。
この主体性・能動性=「アクティブ読解」こそが、文章読解時に最速で本質をキャッチする原動力です。
以下にあくディブ読解における6つのアプローチをご紹介します。
①この話のテーマは何か?
②この話の論点は何か?
③この話の結論は何か?
④結論を支える理由・根拠は何か?
⑤この話の本質は何か?
⑥アウトプットで読解の質を高めていく
表層読解とは、話の内容を正確に把握する読解のことです。
大事なのは<そこに何が書かれているか>であり、それが、行間や背景などの言外情報の読み解きを必要とする本質読解や深層読解と異なる点です。
要約への意識を最大化する魔法の方法が、「『死んでもこれだけは言っておく』としたら何を言う?」と自分に質問してみることです。
話の内容を読み解くうえで、注目すべき品詞のひとつが「接続詞」です。
盲目的に情報を受け入れるだけでは、真の読解力は養われていきません。
主体的かつ積極的に、情報を咀嚼する必要があります。
正しい評価を加えるためにも、「それはあなたの個人的意見なのでは?」と批判的に物事を見る目を養っていきましょう。
発言者や書き手の視点に立ち、「なぜこの言葉を選んだのか」「どのような気持ちで言ったのか」を想像することで、適切なニュアンスを把握しやすくなります。
「もうわかった」と思った瞬間、人はそれ以上に深く考えようとはしなくなります。
「理解したつもり」は、読解における最大の敵です。
情報とは生き物であり、環境や状況、目的によって、その意味は変化します。
(略)
過去の出来事さえ、その意味づけや価値は、時とともに変化します。
だからこそ、「自分はまだ一部しか理解できていないかもしれない」と思うくらいでちょうどよいのです。
■【実践】3個の行動ポイント
【2169-1】知らない言葉に遭遇したら、「○○とは」と「とは検索」することを習慣にする
【2169-2】情報を要約する際は、「『死んでもこれだけは言っておく』としたら何を言う?」と自問する癖をつける
【2169-3】情報に触れたら、「それは相手の個人的意見なのでは?」と自問し精査する
■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】読解力は最強の知性である
【著者名】山口拓朗 ・ 著者情報
【出版社】SBクリエイティブ
【出版日】2025/3/14
【オススメ度】★★★★★
【こんな時に】読む力を身につけたいときに
【キーワード】思考、教養、情報整理
【頁 数】352ページ
【目 次】
第1章 なぜ読解力は最強の知性なのか?
第2章 読解力の前提となる語彙力を鍛える
第3章 本質をつかむための論理力を磨く【本質読解】
第4章 「細かい関係性」を理解する【表層読解】
第5章 クリティカルに聴く・読む【深層読解】
▼さっそくこの本を読む

読解力は最強の知性である
山口拓朗 SBクリエイティブ 2025-3-14
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
山口拓朗さん、素敵な一冊をありがとうございました!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2025年 4月 30日
-
2025年 5月 06日トラックバック:【月間】書評記事アクセスランキングTOP10(2025年4月)
-
2025年 5月 07日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキングTOP10(4/28〜5/4)
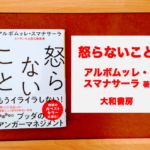
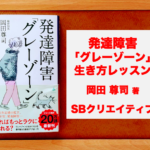
この記事へのコメントはありません。