
【「わかる」から遠ざかれ!】
編集者・佐渡島庸平氏が、『観察力を高める』と題して、正解がない時代を生き抜くには物事を見る”解像度”を高くすることが重要だと提起し、鍛えるべき「観察力」の磨き方を指南する一冊。
■書籍の紹介文
『観察』という言葉。
「言葉の意味は?」と聞かれて答えられますか?
本書は、絶対的な正解のないこれからの時代、観察力の有無が仕事や人生の質を大きく左右すると提起し、客観的になり注意深く観る技術としての「観察力」を磨く方法を指南する一冊。
観察とは
物事の状態や変化を客観的に注意深くみて、組織的に把握すること。
言葉の意味に触れると、観察という行為はとても奥が深いことがわかります。
『客観的』でなければならず、『注意深く』でなければならないのですから。
『客観的』であるためには、この手のテーマでよく出てくる”バイアス”を理解する必要があります。
いかにバイアスの存在に気づき、それらを乗り越えて”まっさらな状態”で物事を見れるかで客観性は決まるからです。
そして、バイアスに気づくためには慎重かつ『注意深く』物事の状態や変化を見る必要があります。
ここまで出来てはじめて、「観察する」という行為が完了するのです。
本書では、「観察する」という能力を鍛えていくための方法がまとめられています。
著者は、『観察力を鍛えると必然的に他の能力も鍛えられる、観察力はまさに”ドミノの1枚目”だ』と断言します。
観察力を鍛えて、物事を見る目の解像度が高くなれば、物事の状態や変化が「わかる」ようになる。
ただ、「わかる」という状態になること自体がバイアスの罠に陥っているのかもしれない。
このように、読み進めるほど禅問答の世界に迷いこんでしまったようで気持ちが悪くなります。
けれども、この気持ち悪さ、モヤモヤの先の境地に辿り着こうとすることこそが大切なようにも感じました。
そのうえでまずできることは、言葉にするということ。
頭の中で考えているかぎりは、バイアスや本能から抗うのは困難です。
見たまま感じたままを言葉にして、言葉という可視化された存在に変換する。
そしてまた、その言葉を観察することで、解像度が高まっていくからです。
「観察する」ために必要な武器が学べる一冊。
興味のある方は読んでみてください。
◆ドミノの1枚目を倒そう。

観察力を高める
佐渡島庸平 SBクリエイティブ 2024-12-20
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
■【要約】15個の抜粋ポイント
経営や創作に役立つ能力とは何かを考えたときに、僕が直感的に思ったのが「観察力」だ。
観察力を鍛えると必然的に他の能力も鍛えられる。
しかし、他の能力を鍛えることを意識していても、観察力の成長はゆっくりだろう。
観察力こそが、ドミノの一枚目だ、と。
いい観察とは、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。
一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる。
観察を阻害するといったとき、ここで紹介した3つの要因ーー
(1)認知バイアス(=脳)
(2)身体と感情(=感覚器官)
(3)コンテクスト(=時空間)
がバグを起こしやすいと意識しているだけで観察の精度は変わってくる。
僕は、この3つを総称して、「メガネ」と呼んでいる。
人間は、メガネをかけて、世界を見ている。
仮説は、観察を始めるときの最強の道具になる。
現代はたくさんの道具がある。
その道具に振り回されると、人は観察ではなく「観測」を行ってしまう。
観測をすると、データーという手触りのあるものが手に入る。
それで、何かを得た気分になり、安心してしまう。
インターネットをはじめとした道具など何もなくても、仮説だけを頼りに世の中を見ていた人たちのほうが、ずっと遠くまで観察できているように思う。
見たものをとにかく言葉にする。
言葉にしていると、自然と問いが浮かび上ってきて、仮説が生まれる。
観察には仮説が不可欠だが、何も思い浮かばないときは、言葉にすることだけを目的に観察を始めるといいと考えているのだ。
仮説を自分一人で磨くのには、限界がある。
自分の仮説にフィードバックをされるのが怖いという人は、多いと思う。
しかし、フィードバックを怖がっていたら、いつまでも同じところにとどまってしまう。
自分の思考法を磨くより、フィードバックをどう受け取るか、フィードバックに対しての観察力を高めることの優先順位を上げるといい。
自分の仮説を強化する情報を見たときに、それを否定せず、より信じるほうにあえて使う。
確証バイアスを意識的に使うことは他者との個人的な関係においては、より相手への尊敬を深めたり、自分の情熱をさらに高めたりといい方向にはたらく。
うまくいかないことがあっても、「大丈夫、やれるんだ」と自分を奮い立たせ続けられる。
全ての人と一期一会の感覚で向き合うことが、人生を豊かにすることだ。
僕はそう考えている。
ハロー効果(後光効果)は、その思想の邪魔をする。
ハロー効果で、メンバーやスタッフとの間に、レッテルを貼った関係が築かれてしまっては、アウトプットにも影響を及ぼす。
だから僕は「正解を知っていそうな佐渡島庸平」という相手のイメージを崩しにかかる。
未来がわからないと、人は不安を感じる。
一方で、その不安は未知のものへのワクワクにもなり得る。
バイアスについて学び、バイアスを武器にして、現実を見る準備ができていると、同じものを見ても、不安ではなく、ワクワクできると僕は考えている。
物語によって、見えないもの(感情と関係性)に気づく能力を鍛えることができ、僕は現実社会と向き合う準備ができたのだと思う。
感情を理解するためにまず大切なのは次の2点だ。
◎感情とは選ばされているのではなく、自ら選んでいる
◎感情にいいも悪いもない
自分の感情を観察する。
すると、自然と行動が変わる。
行動を変えようと意気込んでも、簡単には変わらない。
それよりも、感情を観察して、今注目していることを手放すと自然と感情が変わって、行動が変わる。
感情は自分の心の中にある。
でも、見ることができない。
だから、観察が何も始まらない。
足がかりとして、知識を使って、自問をすることで観察が始まる。
できるだけ無意識で動きたいというのが人の本能なのだ。
本能は、人が無意識の自動操縦で生きられるように導いてくる。
観察とは、それらの無意識で行っている行為を、全て意識下にあげること。
つまり観察とは、本能に抗おうとする行為だ。
「わかる」はまったく理想の状態ではない。
「わかる」から遠ざかろうとして、世の中を観察すると、違う世界が見えてくる。
対象への愛がないといい観察ができない。
愛さえあれば、時間はかかるかもしれないが、いい観察ができる。
そして、いい観察ができると、より愛が深くなる。
■【実践】3個の行動ポイント
【2166-1】「身体感覚」を磨くことを生活習慣に取り入れる
【2166-2】バイアスについて継続的に学習をする
【2166-3】「わかる」という言葉を極力使わないように意識する
■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】観察力を高める
【著者名】佐渡島庸平 ・ 著者情報
【出版社】SBクリエイティブ
【出版日】2024/12/20
【オススメ度】★★★★☆
【こんな時に】明日の仕事力を磨きたいときに
【キーワード】発想力、アイデア、ことばのチカラ
【頁 数】264ページ
【目 次】
第1章 観察力とは何か?
第2章 どうしたら観察力を高めることができるのか?
第3章 なぜ観察力が低いのか?
第4章 見えないものはどう観察するのか?
第5章 観察力を高め続けるために
▼さっそくこの本を読む

観察力を高める
佐渡島庸平 SBクリエイティブ 2024-12-20
Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す
佐渡島庸平さん、素敵な一冊をありがとうございました!
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

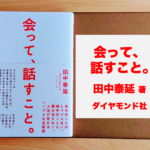

この記事へのコメントはありません。