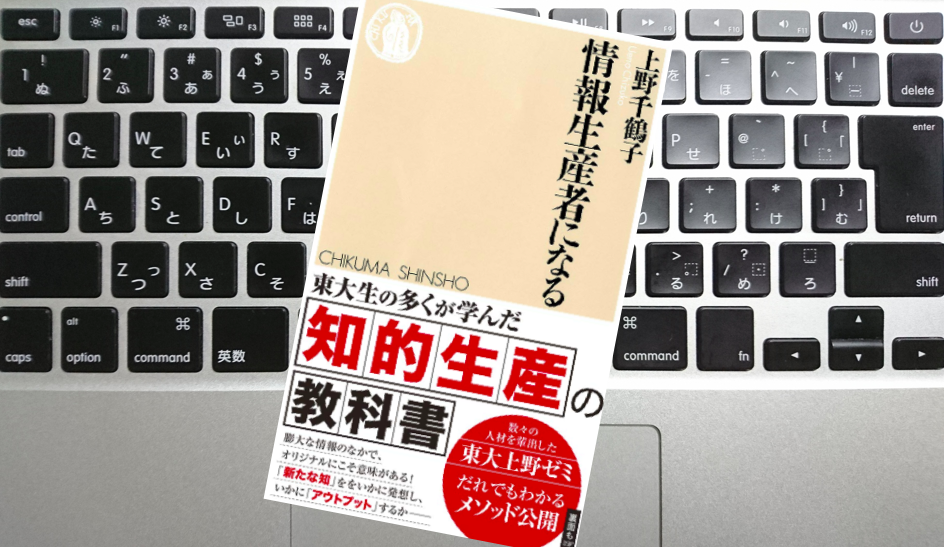
【価値のある情報を生産せよ!】
東京大学名誉教授・上野千鶴子氏が、みずからオリジナルの問いを立て、みずからその問いに答えていく、情報生産者になることを提唱する一冊。発信者になるためのノウハウが満載!
もくじ
■書籍の紹介文
価値のある情報。
ふだん、どれだけ触れているとおもいますか?
本書は、だれもが、答えのない問いに立ち向かい、価値のある情報を生産するために必要なノウハウを解説する一冊。
ふだん何気なく触れている”情報”。
その裏側というか、そもそも情報とはなんなのかに迫っていく内容です。
情報の消費者になるのか、情報の生産者になるのか。
それぞれの姿を見せつつ、後者の生産になることを強く提唱していきます。
情報発信者として学ぶべき教養が書かれています。
発信することがあたり前の現代、真剣に発信する人ほど押さえておくべき内容だと感じます。
アカデミックな内容なので、難読するかもしれません。
ですが、ゆっくりでもいいので頑張って読んでみて下さい。
読み終わるとき、情報発信者として一皮剥けることでしょう。
そして、価値のある情報生産者の一歩を踏み出すのです。
◆新たな知を生み出そう!
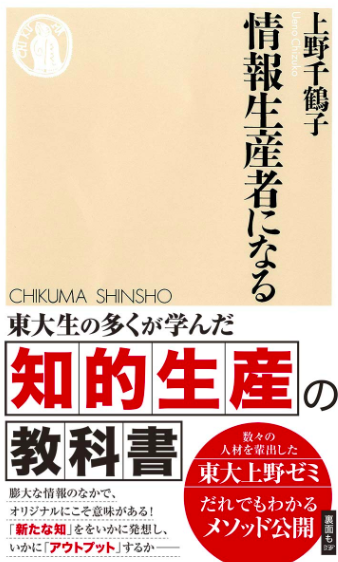
情報生産者になる
上野千鶴子 筑摩書房 2018-9-6
売上ランキング(公開時):3,083
Amazon Kindle 楽天
■【要約】15個の抜粋ポイント
情報を生産するには問いを立てることが、いちばん肝心です。
●問いを立てる際の2つの条件
(1)答えの出る問いを立てること
(2)手に負える問いを立てること
オリジナルであるためには、すでにそこに何があるかを、知らなければなりません。
すでにそこに何があるかという膨大な情報の蓄積を知っていることを、「博識」とか「教養がある」といいます。
が、教養があるだけではオリジナリティは生まれません。
反対にオリジナルであるためには教養が必要です。
教養とオリジナリティは相反するものではなく、ほんらい補完しあうものです。
「批判的」とは、そこにあるものではなく、そこにないものを見抜く力を言います。
問題が問題になるのは、現状に満足できない誰かが、それを問題と言い立てるからにほかなりません。
ビッグデータ万能みたいなデータ・マイニングがおもしろくないのは、しょせんキーワード分析や関連語分析しかできず、言説分析ができないからです。
情報とは語ではなく言説。
意味のあるセンテンスであればOKです。
要約には必ず書き手のバイアスやノイズが入ります。
一次情報の生産過程において、ノイズをなくすことはできません。
ノイズは入るもの、とハラをくくります。
インタビューは議論や反論の場ではありません。
たとえ相手のいうことに同意できなくても、相槌を打ちましょう。
相槌は同意ではありません。
そして「どうしてそうお考えなのですか?」と相手をよりよく理解するようにしましょう。
そこに何があるかだけでなく、何がないかにも配慮します。
プレゼンとは思考の過程よりは思考の結果を示すことです。
目次を見れば書き手のアタマのなかがわかる
必要な本はかならずアンダーラインを引きながら読みます。
本は汚すもの。
ですから書物は購入して自分の所有物にしたほうがよいのです。
愚にもつかない質問はスルーすればよいのです。
スルーの仕方にも芸があります。
いちばん簡単なのは、問いには問いで返すこと。
情報生産者とはまだ見ぬコンテンツを世に送る者たち。
そしてそれを公共財にしたいと願う者たちです。
そのためにはあなた自身が「今・ここにないもの」を夢みる能力を持っていなければなりません。
■【実践】3個の行動ポイント
【1446-1】情報生産の過程で、ノイズは入るものとハラをくくる
【1446-2】読む場合も書く場合も、目次を大切にする
【1446-3】「今、ここにないもの」を常に意識する
■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作
■本日の書籍情報
【書籍名】情報生産者になる
【著者名】上野千鶴子
【出版社】筑摩書房
【出版日】2018/9/6
【オススメ度】★★☆☆☆
【こんな時に】教養を伸ばしたいときに
【キーワード】教養、情報発信、情報整理
【頁 数】381ページ
【目 次】
1 情報生産の前に
2 海図となる計画をつくる
3 理論も方法も使い方次第
4 情報を収集し分析する
5 アウトプットする
6 読者に届ける
この本が、あなたを変える!
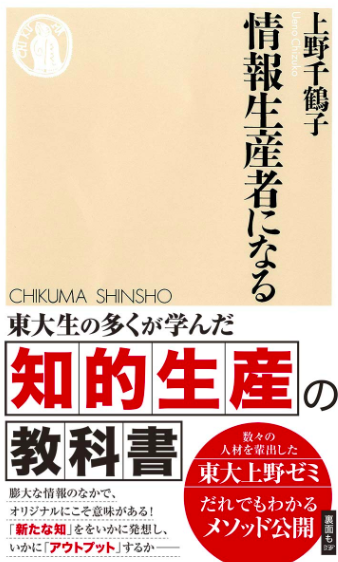
情報生産者になる
上野千鶴子 筑摩書房 2018-9-6
売上ランキング(公開時):3,083
Amazon Kindle 楽天
上野千鶴子さん、素敵な一冊をありがとうございます\(^o^)/
■お知らせ
■【仲間大募集中!】101年倶楽部■
書評ブロガーの読書術を教えていきます。
読書の質を高めたい方は、ぜひご参加下さい!

■応援お願いします!■
※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。
コメント
-
2019年 7月 02日
-
2022年 11月 10日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(10/31〜11/6)
-
2022年 11月 14日トラックバック:【週間】書評記事アクセスランキング(11/7〜11/13)
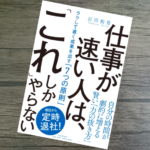

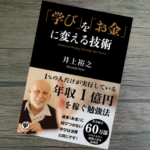
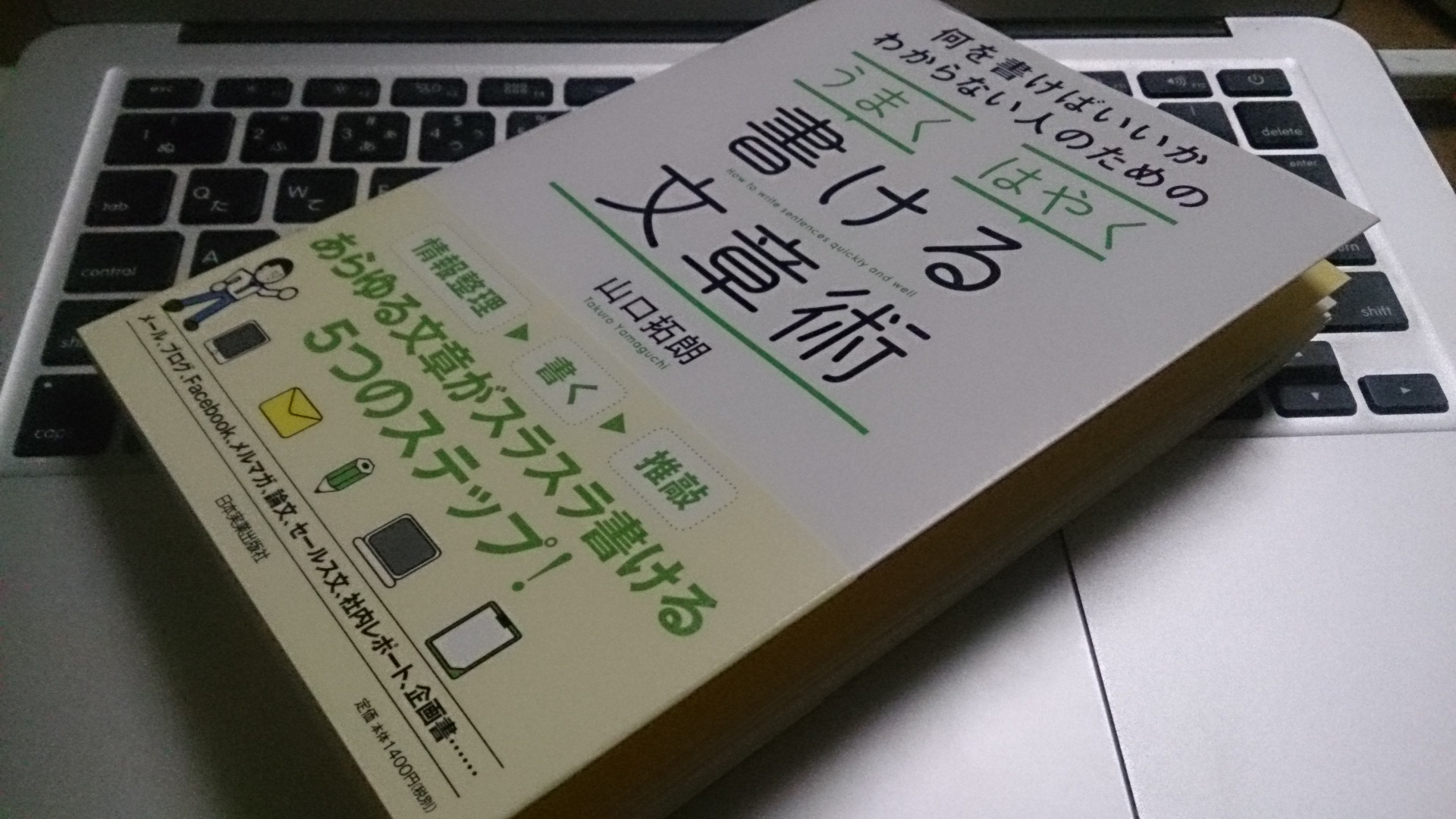
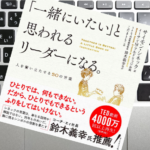
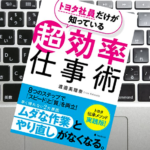
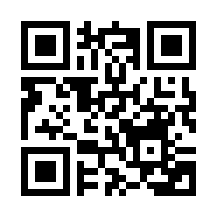
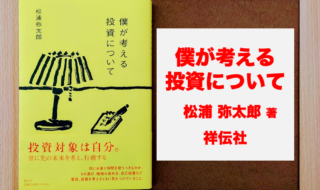
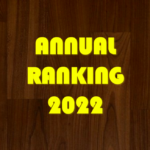

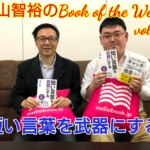
この記事へのコメントはありません。